DS39xx CCFLコントローラによるアナログ調光の実装
要約
DS3881、DS3882、DS3988、DS3991、DS3992およびDS3994は液晶ディスプレイ(LCD)のバックライト用の冷陰極蛍光管(CCFL)用のコントローラです。ほとんどのアプリケーションでは満足のゆく視覚効果またはランプ寿命を確保するために調光が必要になります。このアプリケーションノートではCCFLに通常使用されている2つの調光法を最初に紹介します。その後、CCFLコントローラのDS39XXのアナログ調光の実装方法について説明します。
CCFLの調光方法
CCFLの調光には2つの良く知られた方法があります。PWM調光もしくはディジタル調光と呼ばれているバースト調光とアナログ調光です。この論文はこの各方法の長所と欠点について説明します。
バースト調光はPWM調光周波数と呼ばれる、ある一定の周波数でCCFLをオン/オフします。PWM調光周波数が60Hzよりも高いと、人間の目はCCFLがオンとオフにスイッチングしていることを検出することができません。PWMサイクルのハイ期間にはCCFLはオンになっており、ランプ周波数で動作しています。PWMサイクルのロー期間にはCCFLはオフになっており、ランプには電流が流れません。PWMパルスのデューティサイクルを調整することによって、CCFLの明るさを増加したり、減少させたりすることができます。バースト調光の主な利点は非常に大きい調光比を実現可能なことです。しかし、アプリケーションによってはPWM調光周波数が表示信号の垂直同期周波数に干渉する可能性があり、このため、画面上の視覚に影響します。バースト調光は可聴のトランスノイズを生じる可能性もあります。
CCFLをバーストでオンにする代わりに、アナログ調光はCCFLを連続してオンのままにします。ランプの明るさはランプ電流振幅を変えることによって調整します。言うまでもありませんが、電流振幅を大きくするとCCFLが明るくなり、振幅を下げるとCCFLは暗くなります。アナログ調光の範囲は非常に狭く、アプリケーションによっては不十分です。しかし、アナログ調光は可聴トランスノイズを生じることはありません。それはPWM周波数が存在しないからです。 さらに、アナログ調光は垂直同期周波数と干渉しません。
表1はアナログ調光とバースト調光を比較しています。アプリケーションノート3997にはさらに詳細な情報があります:How to Achieve a 300:1 Dimming Ratio with the DS3881/DS3882 CCFL Controllers.
| Analog Dimming | Burst Dimming |
| 1. Narrow dimming range, no more than 3:1 | 1. Large dimming ratio up to 100:1 |
| 2. No audible transformer noise | 2. Audible transformer noise can be present. |
| 3. No interference with the vertical synchronous frequency | 3. The PWM dimming frequency can interfere with the vertical synchronous frequency. |
CCFLアナログ調光の実装
DS3881およびDS3882のCCFLコントローラにはアナログ調光制御機能が組み込まれています。ランプ電流はI2Cインタフェースを用いてBLCレジスタを設定することによって調整可能です。
DS3988、DS3991、DS3992、およびDS3994のCCFLコントローラはバースト調光を備えています。しかし、図1に示すように簡単な外付け回路を使って、これらのDS39XXコントローラによって実質的にアナログ調光を行うことができます。

図1. DS39XXのCCFLコントローラでアナログ調光を実装するために必要な外付け回路
図1でR4がランプ電流のフィードバック抵抗です。R4の両端間のピーク電圧レベルがVR4です。信号がダイオードを通過すると、ピーク電圧レベルがVAとなります。LCM入力でのピーク電圧レベルのVLCMはVAとアナログ調光制御電圧VDIMの線形結合になります。したがって、

ここで、
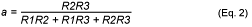
そして

VLCM (ピーク値)は公称2.35Vです。したがって、VDIMがVAを決定し、VAがランプ電流に直接関係します。R1が開放となってVDIMが有効ではない場合は、回路は事実上DS3992/DS3994のデータシートに示される標準的な複数ランプ電流のモニタ回路の一部になります。
抵抗値の計算
抵抗値を計算するためには、aとbを得るためにシステム要件を使用します。その後、式2と式3を使ってR1、R2、およびR3の適切な値を計算します。
例えば、VDIMが0Vの時にランプ電流が7mARMS、VDIMが3.3Vで3mARMSとアプリケーションが要求する場合、VDIM = 0VでVAが19.1Vpk (√2 × 7mARMS × 2kΩ - 0.7V)に等しく、またVDIM = 3.3VでVAが7.8Vpk (√2 × 3mARMS × 2kΩ -0.7V)に等しくなります。これらの条件と式1を用いてa = 0.422、b = 0.123と決定することができます。
aとbが決まったので、今度はR3を任意の値にします(10kΩを超えないでください)。その後で、式2と式3によってR1とR2を決めます。R3を3.4kΩとすると、R1は3.65kΩ、R2は12.4kΩになります。ランプは高調波を含んでいるため、電流波形の波高因子が√2になるとは限りません。したがって、所望の結果を得るためには抵抗値の調整が必要になります。この場合、R1とR2の最終値はそれぞれ4.42kΩと11.5kΩになります。
上述のアプリケーションではランプ電流は調光電圧を大きくすると減少します。この機能は負傾斜の調光と呼ばれます。逆に正傾斜の調光では調光電圧を大きくすると、ランプ電流が増加します。正傾斜調光が所望の場合は、VDIMとR1の間に反転回路を加えると可能になります。
測定波形
図2と図3には図1の回路に基づく測定されたランプ電流波形が示されています。図2はVDIM = 0Vでの波形です。図3はVDIM = 3.3Vの波形です。この場合の調光比は2.33:1です。
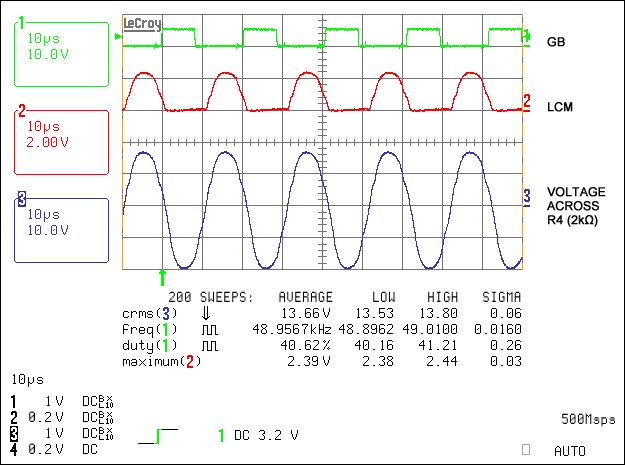
図2. VDIM = 0Vでのランプ電流波形
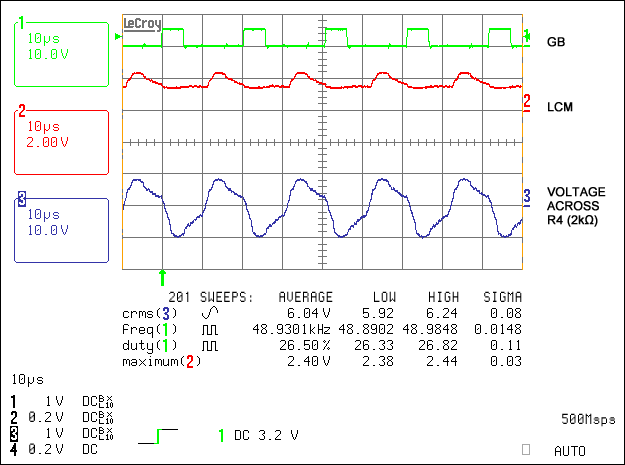
図3. VDIM = 3.3Vでのランプ電流波形