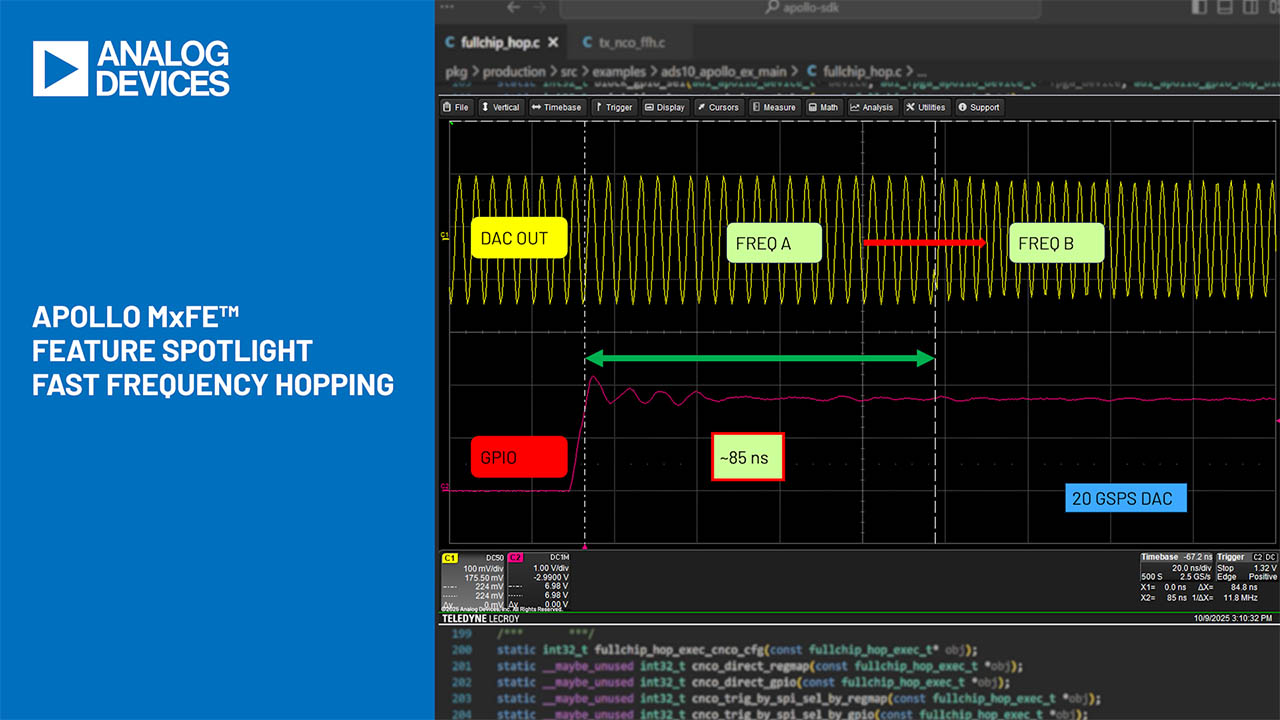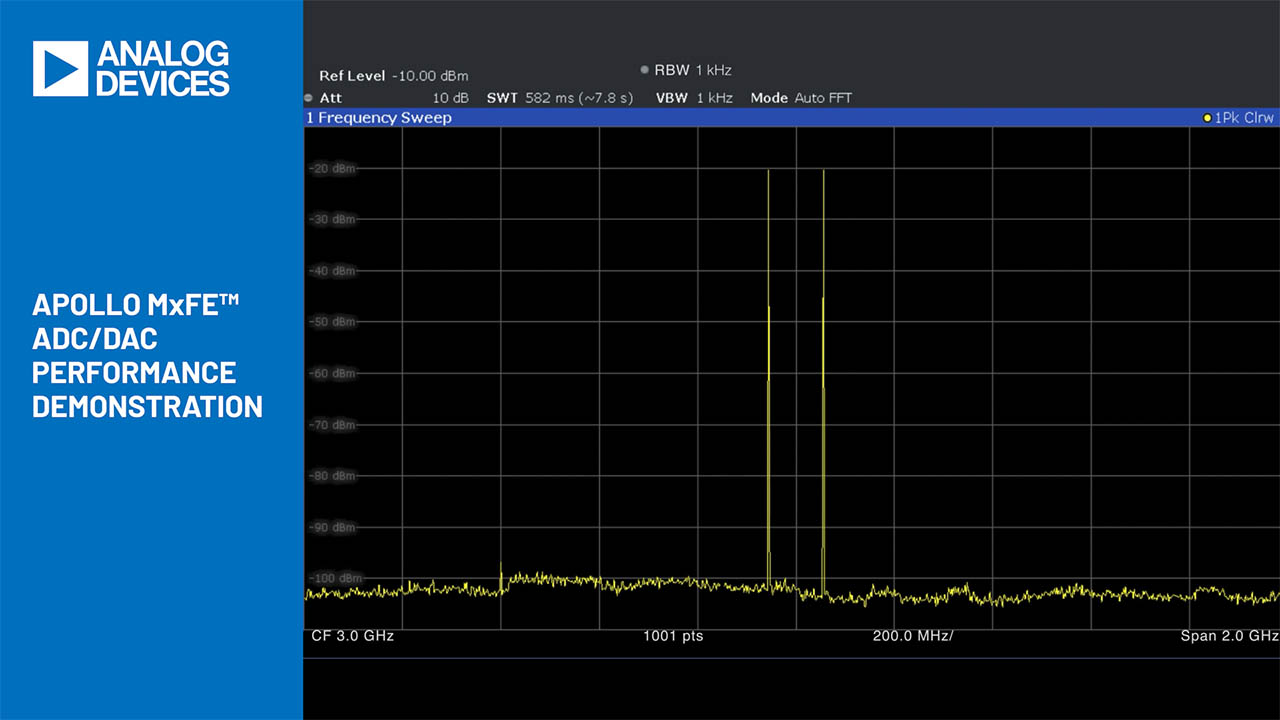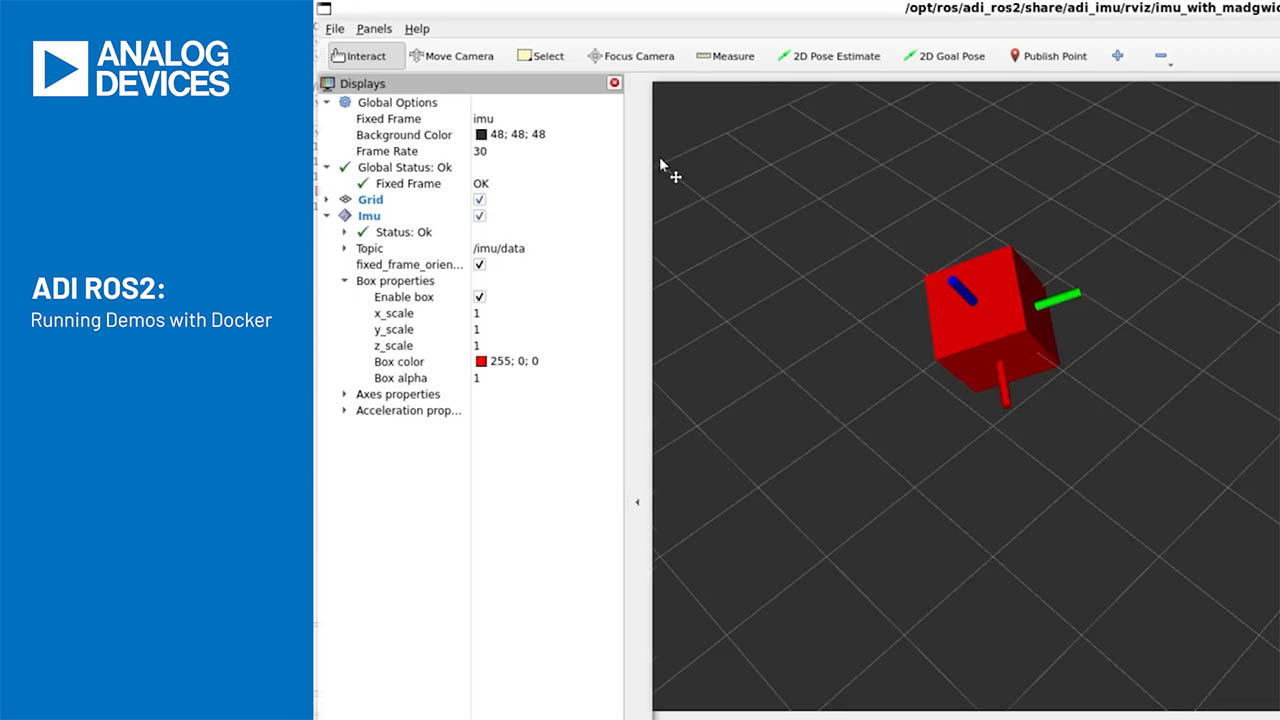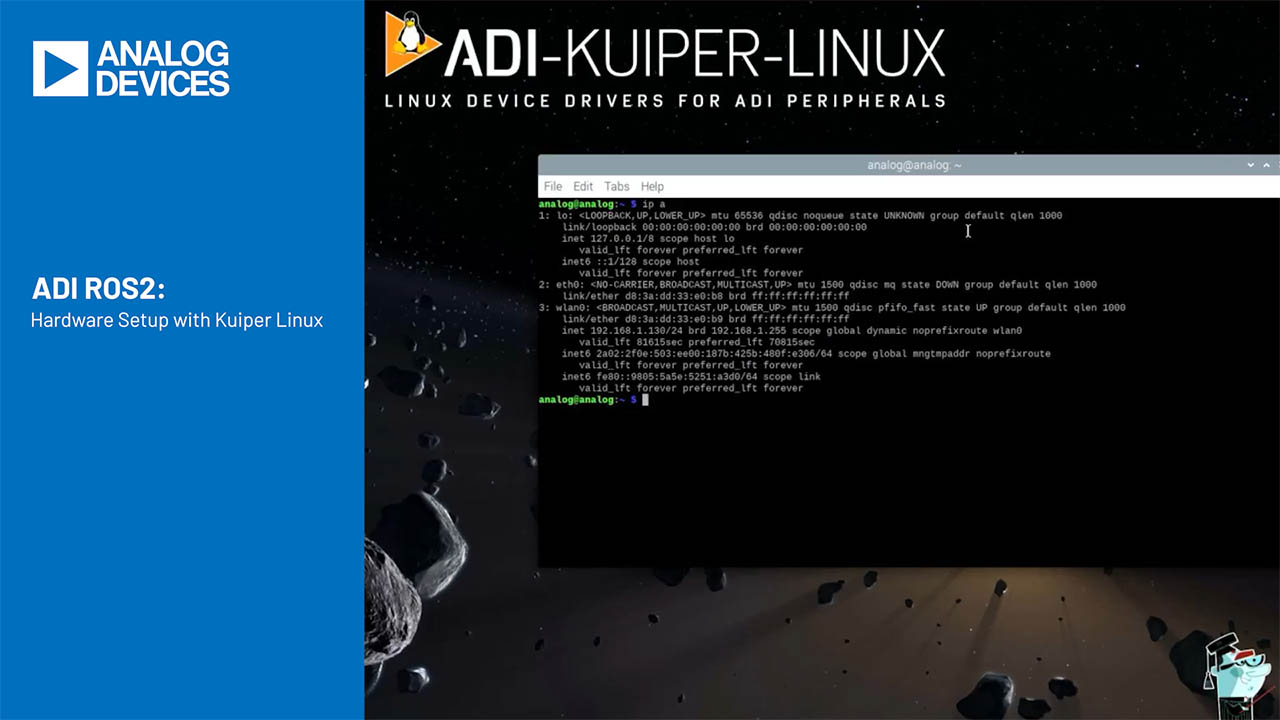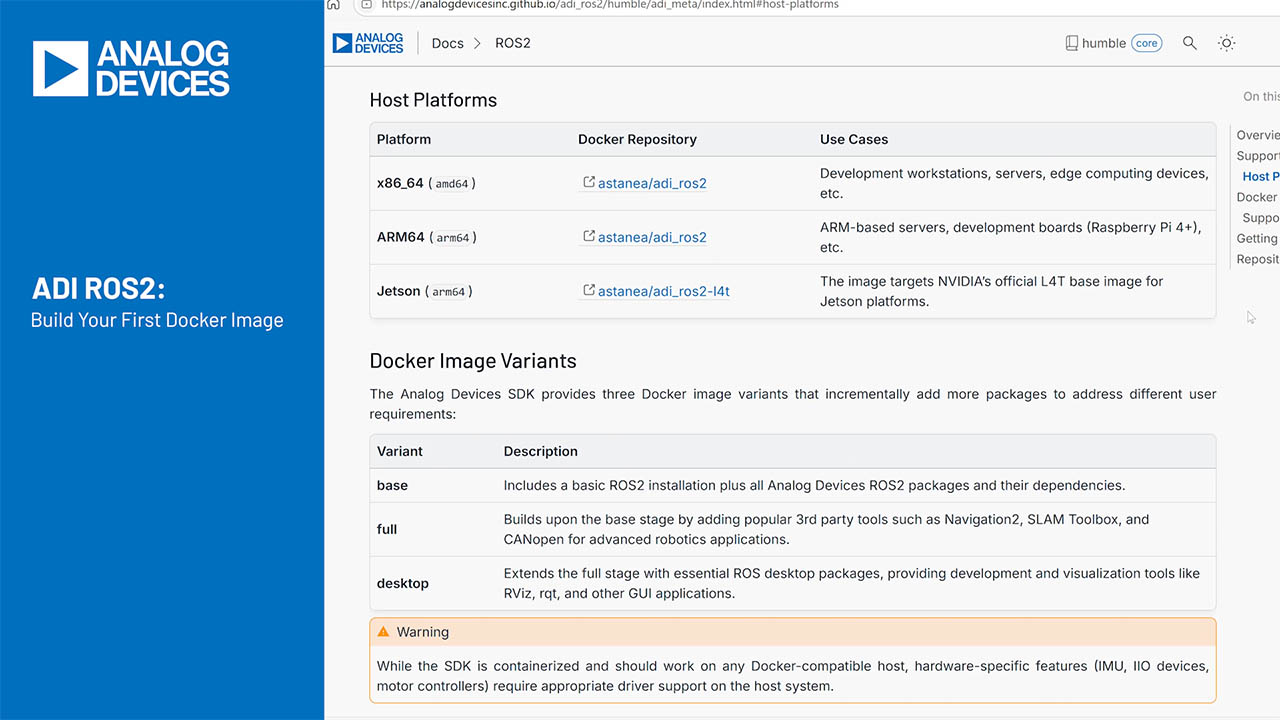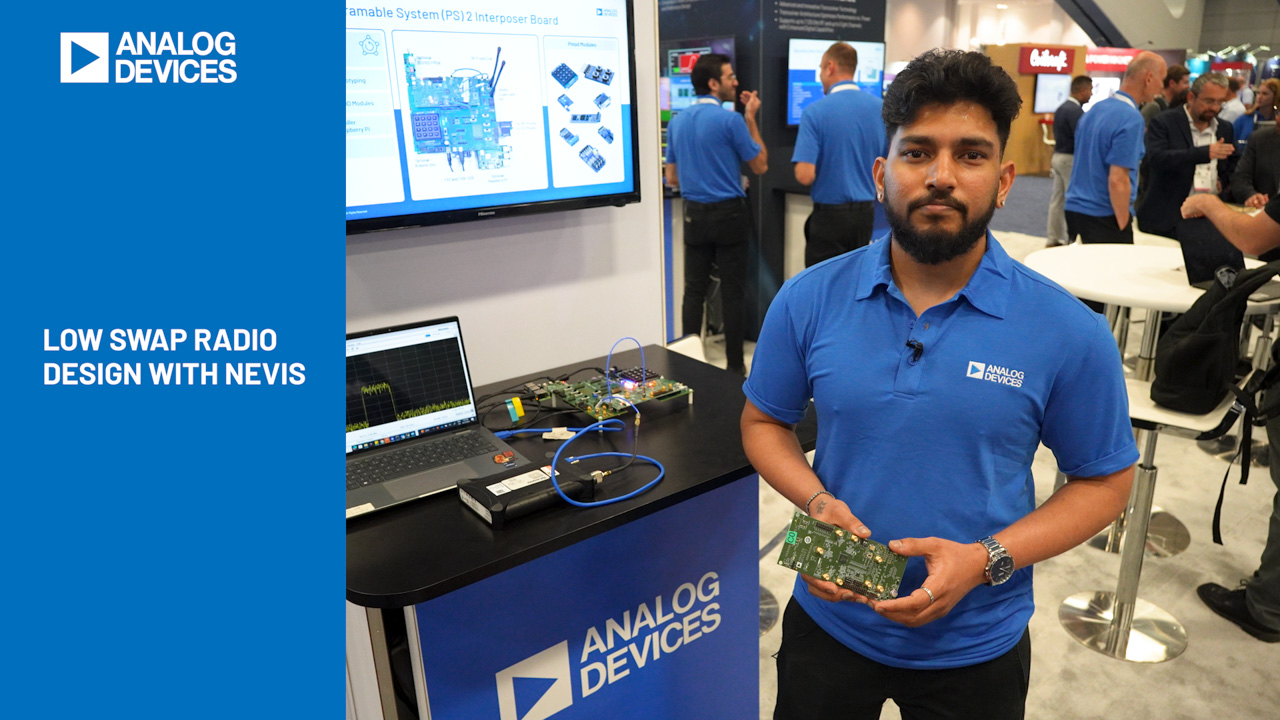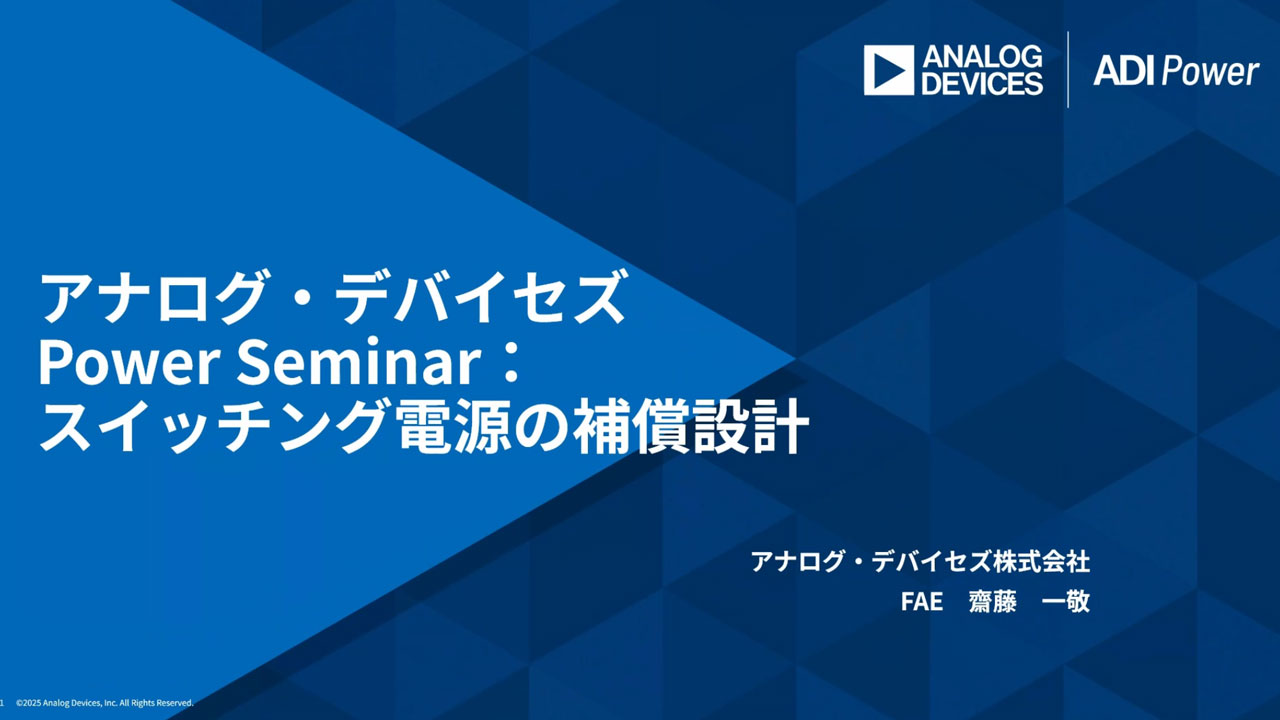要約
送信側のプリエンファシスと受信側のイコライゼーションを行うと、安価なケーブルでも長距離間でシリアライザ/デシリアライザ(サーデス)デバイスを運用することができます。このアプリケーションノートでは、ケーブル上で起こる信号劣化の仕組みや、そうした劣化を補償する方法について説明します。さらに、損失の多いケーブルを使用する場合に、マキシムのギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)製品によって安定したリンクを実現する方法について説明します。また、このアプリケーションノートでは、ラインイコライゼーションについても概説します。
同様の記事が2011年11月2日に「John Day's Automotive Electronics News」に掲載されました。
はじめに
ビデオアプリケーションにおける最近の進歩や、データトラフィック量の急激な増大に伴って、ますます高いデータレートが求められるようになっています。その結果、特に低コストなツイストペア(TP)ケーブルに関心が寄せられています。しかし、長距離にわたって敷設されたTPケーブルで起こる周波数依存減衰は、これらのケーブルの最適な利用にとって重大な制約要因の1つです。この周波数依存減衰は、受信信号に重大な符号間干渉(ISI)を引き起こすため、クロックとデータの復元が困難となり、ビットエラーレート(BER)が増大します。図1は、送信された信号がケーブル上で劣化した後、レシーバに着信する様子を示しています。トランスミッタとレシーバで何らかのラインイコライゼーションを利用し、ISIを大幅に低減して重度に劣化したデータを復元することによって、信頼性の高い動作を実現することができます。

図1. レシーバ側でのISI
マキシムのGMSL部品では、システム設計者がそれぞれのケーブルに応じてイコライゼーションレベルを動的に設定可能であるため、高速な3.125Gbpsトランシーバによって安定したリンクを実現することができます。トランスミッタとレシーバの両方に、個別にまたは同時にプログラム可能なイコライゼーションの調整があることにより伝送距離を延長することが可能です。こうした柔軟なイコライゼーションの調整によって、損失の多い低コストなケーブルを幅広く利用することができます。
このアプリケーションノートでは、マキシムのGMSL製品と損失の多いケーブルによって安定したリンクを設計する方法を説明します。また、ラインイコライゼーションについても概説します。
GMSLにおけるトランスミッタ側のプリエンファシスとレシーバ側のイコライゼーション
GMSLリンクでは、トランスミッタ側でプリエンファシス、レシーバ側でイコライゼーションを行って伝送の損失を補償します。
トランスミッタ側のプリエンファシス
レシーバ側でイコライゼーションが適用されていなければ、図2に示すとおり、「1」の連続信号の後に「0」の高周波パルスが信号振幅の中央レベルに達することができない場合があります。この図は、遷移部分を強調し、「無遷移部分」にデエンファシスを適用することによって、周波数依存減衰を克服することができることを示しています。

図2. 時間領域のプリエンファシスフィルタリング
ケーブルには、図3に示すように、導体損失と誘電損失によるローパス伝達特性があります。イコライゼーション(ハイパス伝達曲線)を利用することによって、目的の周波数範囲の帯域幅内でフラットな(減衰が均一な)システム周波数応答を実現することができます。

図3. 周波数領域のプリエンファシスフィルタリング
こうしたイコライゼーション手法を効果的に利用すると、3つの主なシステム設計パラメータに影響を与えることができます。
- ケーブル長
- ケーブルタイプ
- 最大システムデータレート
たとえば、10mのケーブルの末端でアイダイアグラムが完全に閉じる場合、6dBのプリエンファシスによって妥当な広さの開口部が得られます(図4)。

画像の拡大(PDF, 1.3MB)
図4. 10mのケーブルによる3.125Gbpsデータ伝送に(a)処理を適用しない場合と(b) 6dBのプリエンファシスを適用した場合の比較
MAX9259のデータシートに記載されているとおり、プリエンファシスのレベルはレジスタアドレス0x05、D[3:0]で設定されます。ユーザーは、表1に基づいてプリエンファシスのレベルを設定することができます。負のプリエンファシスレベルは高周波の項を強調せず、低周波の項にのみデエンファシスを適用する場合に相当します。オーバーブーストによってタイミングジッタがわずかに増大することにも注意してください。
| 0x05 D[3:0] | Preemphasis Level (dB) |
| 1000 | 1.1 |
| 1001 | 2.2 |
| 1010 | 3.3 |
| 1011 | 4.4 |
| 1100 | 6.0 |
| 1101 | 8.0 |
| 1110 | 10.5 |
| 1111 | 14.0 |
| Deemphasis Level (dB) | |
| 0000 | Not Used |
| 0001 | -1.2 |
| 0010 | -2.5 |
| 0011 | -4.1 |
| 0100 | -6.0 |
| 0111 | Not Used |
以下のセクションでは、トランスミッタとレシーバの両方のイコライザを利用する方法を説明し、試験データの表も示します。
レシーバ側のイコライゼーション
レシーバ側におけるイコライゼーションの背景となる基本的な考え方を図5に示します。リンクの損失が多い場合、データ周波数に比べてはるかに狭い帯域幅を持つ近似的な1次伝達関数に従って順方向のチャネルデータが減衰します(データ周波数fbはビットレートの半分に等しい)。それによる符号間干渉の結果、デターミニスティックジッタが発生します。さらに、こうした損失の多いケーブルの末端におけるアイダイアグラムは、ケーブルが長い場合、完全に閉じることがあります。この損失を補償するため、データはまず伝達関数によって処理され、それてそれは理想的には、ケーブルの伝達関数の逆関数になります。これにより、リンクとイコライザがカスケード接続されていれば、十分な帯域幅を得ることができます。GMSLのデシリアライザには、さまざまなケーブル長でアンダーブーストやオーバーブーストを防ぐために、利得を12段階に設定可能な方式が実装されました。2dB~13dBの範囲で、12の異なるブーストレベルに利得を設定することができます。

図5. レシーバ内でチャネルの伝達関数の逆関数を適用することによってデータをイコライズ
さまざまなブースト設定におけるレシーバの伝達関数(AC特性)を図6に示します。10mのSTPケーブルについて、チャネルとレシーバの伝達関数を図7に示します。この図では、さまざまなブーストレベルが重ねて表示されています。総合的な伝達関数は、ブーストワードが8 (9.4dB)のときに、議論の周波数範囲内で最もフラットになります。10mのSTPケーブルについてレシーバ入出力のアイダイアグラムを図8に示します。イコライザの利得ブーストによって完全に閉じたアイダイアグラムが開く様子を確認することができます。
総合的な伝達関数がフラットでない場合はどうなるでしょうか。ISIジッタに関しては、オーバーブーストの方がアンダーブーストよりも害が少ないといえます。図9に示すように、ブーストレベルが最適値を下回ると、出力ジッタが急激に増大します。それに対して、ブーストレベルが最適ポイントを上回ると、ジッタはゆっくりと増大します。

図6. さまざまな調整ワードに対するイコライザのAC特性と利得ブースト

図7. 10mのSTPケーブルを使用した場合のさまざまなブーストレベルに対するケーブルとイコライザ(カスケード接続)のAC応答

図8. 10mのケーブルを使用した場合の最適ブースト時におけるレシーバ入出力のアイダイアグラム
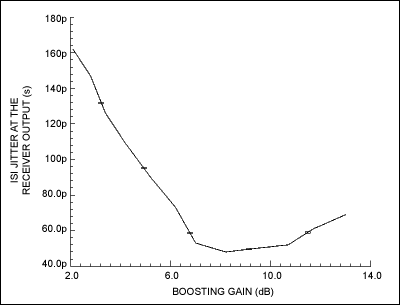
図9. 10mのケーブルを使用した場合のピーク間のISIジッタと利得ブーストの関係
プリエンファシスとイコライザの最適な設定の選択
スペクトルアナライザでケーブル損失を測定するのは、それほど簡単なことではありません。そうした場合に、プリエンファシスとイコライザの最適な設定を選択するための最も簡単な方法は、限界周波数におけるシステムのビットエラーレートを確認することです。ここでは例として、2つの現実的な事例を取り上げます。
表2は、MAX9259/MAX9260やMAX9249/MAX9268などのサーデスペアを10mのケーブルで運用可能な最大ピクセルクロック周波数をまとめたものです。各列は受信側のイコライザのブースト利得を示し、各行は送信側のさまざまなプリエンファシス値に対応します。試験対象のサーデスペアは伝送媒体にイコライズが正しく適用されている場合、最大124MHzで動作可能です。最小の総合ブースト14.1dB (1.1dBのプリエンファシスと13dBの受信側イコライゼーション)の場合に124MHzに達します。総合ブーストが18.2dB (14dBのプリエンファシスと4.2dBの受信側イコライゼーション)を超えた後、ISIは再び増加し始め、動作周波数を制限します。そのため、14.1dBと18.2dBの間で総合ブースト値を選択するのが賢明です。一般に、ブーストの大部分は受信側から選択することが推奨されます。受信側のイコライザは低周波利得が一定であるのに対して、送信側ではプリエンファシスの実装に伴って低周波が減衰するためです。低周波の減衰はリンクの信号レベルが低下し、レシーバの動作が困難になることを意味します。そのため、3.3dBのプリエンファシスと13dBの受信側ブーストが優れた選択となります。15mのケーブルにも同じ手順を適用することができます。さまざまなブーストレベルに対する最大周波数を表3にまとめています。最小と最大のブーストレベルはそれぞれ19.7dB (8dBのプリエンファシスと11.7dBの受信側イコライゼーション)と23.4dB (14dBのプリエンファシスと9.4dBの受信側イコライゼーション)であるため、8dBのプリエンファシスと13dBの受信側ブーストが最適な選択です。

より詳細な画像 (PDF, 54KB)
リンクアクティビティ検出回路
GMSLのデシリアライザには、リンク上に信号がないときにレシーバを停止させる信号検出回路が内蔵されています。長いケーブルや高いプリエンファシスレベルのために信号レベルが非常に低いときに、デシリアライザでリンクのアクティビティを検出することができない場合があります。そのため、10mを超える長いケーブルでプリエンファシスとイコライザの最適な設定を探す間は、アクティビティ検出回路を無効にすることが強く推奨されます。検出回路は、「0x80」をデシリアライザのバイト11に書き込むことで無効にすることができます。最適な値を選択した後に「0x20」を同じバイトに書き込めば、再び有効にすることが可能です。マキシムの測定結果によると、アクティビティ検出回路は、15mのケーブルでは104.16MHzの最大PCLK周波数で最大8dBのプリエンファシスまで機能します。アクティビティ検出回路には、低スレッショルドのオプションもあります。このオプションは「0x00」をバイト11に書き込むことで設定可能です。測定結果によると、アクティビティ検出回路は、低スレッショルドを選択した場合、15mのケーブルで最大14dBのプリエンファシスまで機能します。ケーブル長が15mを超え、プリエンファシスが14dBである場合は、アクティビティ検出回路を無効にすることが推奨されます。これらの測定で使用したケーブルは、標準的な自動車用STPケーブルです。