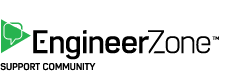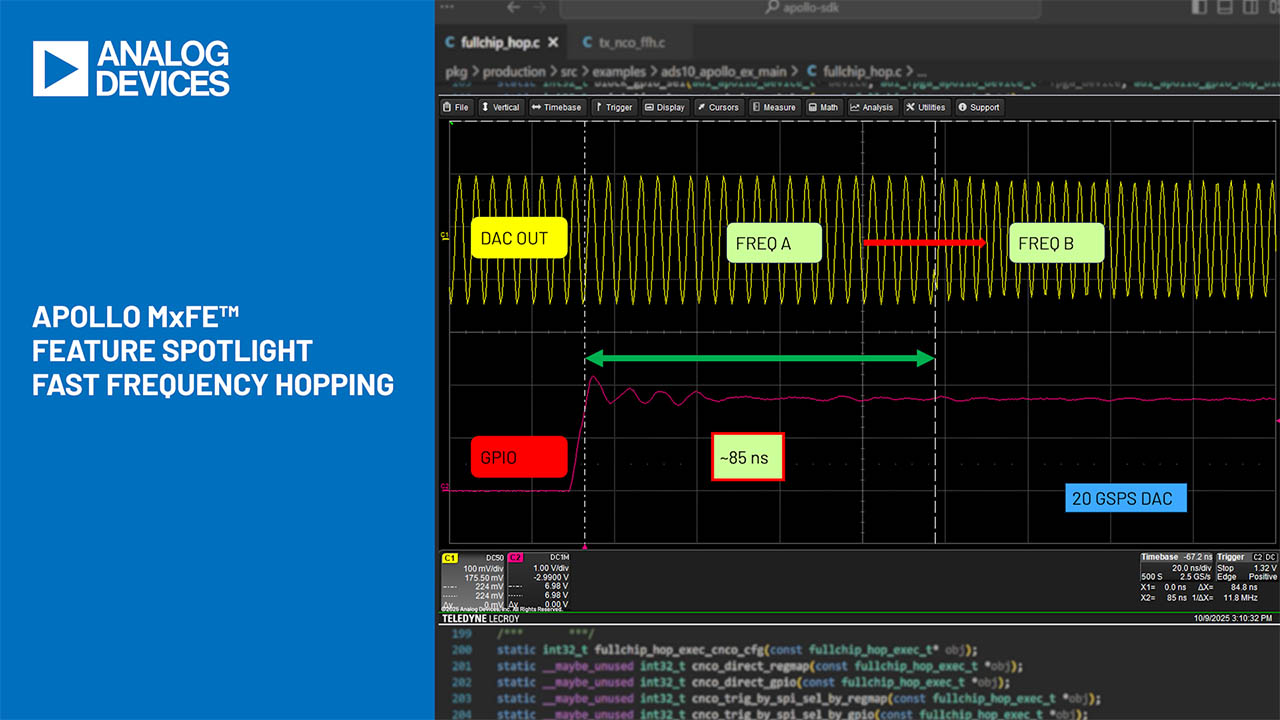FGとSGは、どう処理するべきなのか?
質問
設計済みの回路を筐体などに組み込んで機器/装置を構築する際、FG(フレーム・グラウンド)とSG(シグナル・グラウンド)はどう処理するのが正しいのでしょうか?
回答
質問にあるFGとは、筐体(シャーシ)の基準電位(グラウンド)のことです。一方のSGは、信号線の基準電位のことを表しています。従来、質問者の方は、FGは接地(アース)し、SGはFGに対してフローティングの状態で設計することが多かったそうです。その理由は、「先輩諸氏から、FGの変動やその他の影響を受けて、回路が誤動作したり破損したりすることがないように、そのように処理すると教わったから」だと言います。質問者自身も、微弱な制御信号の基準電位(SG)が外部に対してさらされる状態になるのは危険すぎると感じていたので、その考え方には納得していました。

オーディオ・アンプの中身
ところが、いろいろと調べてみた結果、「その理論は“迷信”とでも言うべきものだ」という意見も散見されました。あるいは、「ノイズ耐性や安全性の面からはFGとSGは互いに接続する方が適切だ」という見解も目にしたそうです。果たして、FGとSGはどのように処置するのが正しいのでしょうか。
結論から言えば、どうやら唯一の正解というものは存在しないようです。そこで、以下では「アナログ電子回路コミュニティ」に技術者の方から投稿された意見や考え方をいくつか紹介することにします。
グラウンドの処置はケースバイケースで
ある投稿者は、EDN Japanに掲載された「グラウンド配線の考え方」という記事を紹介していました。この記事に書かれているのは、グラウンドの処理については、信号の流れを理解し、それに応じて対処することが重要だということです。
つまり、適切な対処というのはそれぞれのケースによって異なるという見解です。FGとSGの関係についても、この考え方が当てはまるとしています。ある意味、質問者の疑問に対してはこれが正解だと言うこともできるのでしょう。この技術者は、FGとSGについては何も考えずに不用意につないではならないとしつつ、一般論としてFGとSGの間を100kΩ(定格電力は1/4W)の抵抗でつないでおくという方法を1つの例として推奨しています。
安全性の確保を重視
別の投稿者は、経験的にFGのことを保安アース(保安グラウンド)だと捉えていると説明していました。一方のSGについては、必要に応じて強固な接続にしたり、デカップリングを施したりといった処置を行うことが重要であり、FGとは切り離して考えるべきだと述べています。加えて、現在では金属製の筐体が使われなくなってきているので、そもそもFGが存在しない例も増えていると指摘しています。
このように、FG自体が存在し得ない場合はともかくとして、それなりに高い電圧を使用する回路がプリント基板に実装されており、なおかつ金属製の筐体も使われている場合には、その筐体に対し、どこか1点でFGとしての接続を行っていると言います。その背景にあるのは安全性の問題です。
例として、オシロスコープで高電圧のインパルス信号を計測するケースを考えます。その際、使用しているいずれかの装置で保安アースの接続を怠っていると、オシロスコープのパネルを触った瞬間に感電してしまうおそれがあります。2つの装置の間でSGと信号線がつながっていれば、とりあえず正常な動作は得られます。ただし、測定にかかわる人物を含めたシステム全体で見ると、思いもよらぬ大きな電位差が生じている個所が存在する可能性があるということです。あるいは、絶縁用の筐体を使用しているので、絶対に危険な場所に触れることはないと思っていても、同軸ケーブルのコネクタを抜き差ししただけで感電してしまうこともあり得ます。別の例を挙げると、PC製品の中には、金属製の筐体を採用しているのに保安アースを設けていないものが存在します。その場合、筐体に触ると、いずれかのLEDがぼーっと発光するといったことも起きるそうです。さらに、交流電圧を使用している場合には、容量性の結合に起因する影響が及ぶことになります。つまり、フローティングにしているつもりなのに、実際には完全なフローティングの状態にはなっていないということも多いということです。
プリント基板設計の変化
さらに、ある投稿者はプリント基板の進化の影響について触れています。多層基板が技術的に確立する前は、グラウンドへの接続にもパターン配線を使用していました。いわゆる“ベタ・グラウンド”と比べると、グラウンド(SG)のインピーダンスは非常に高かったということです。この状態で、FGとSGを不用意につなぐと、よりインピーダンスの低い方向に電流が流れます。その結果、FGのインピーダンスが低い場合には、ノイズが混入するといった予期せぬ不具合が生じることがありました。このような背景から、当時はフローティングや1点接地といった考え方が一般的になっていったのです。インターネットで「共通インピーダンス」、「迷走電流」などの用語を検索すると、詳しい解説が見つかるはずです。あるいは、伊藤健一氏が執筆したアースとノイズに関する解説本や、同氏が監修を務めた「ノイズ対策ハンドブック」といった書籍も参考になるでしょう。
現在では、多層基板の技術が確立され、ベタ・グラウンドが一般的に使われるようになりました。そのため、ほぼ確実に、SGのインピーダンスはFGのインピーダンスよりも、はるかに小さくなります。その結果、FGの多点接続を行っても特に問題はない(迷走電流が筐体を流れることはない)という考えが広まってきました。むしろ、EMC(電磁両立性)の観点から、FGとSGはできるだけ密に接続することが望ましいとされるようにもなっています。
とはいえ、当然例外もあります。EMCが問題になりそうな場合と、製品の安全性が問題になりそうな場合とでは、それぞれにあるべき姿は異なります。まずは、「どうあるべきか」ではなく、「どうしたいのか」ということを明確にしなければ正解にはたどり着けないでしょう。
アナログ電子回路コミュニティとは
アナログ電子回路コミュニティは、アナログ・デバイセズが技術者同士の交流のために提供していた掲示板サイトで、2018年3月に諸般の事情からサービスを終了しました。
アナログ電子回路コミュニティには日々の回路設計活動での課題や疑問などが多く寄せられ、アナログ・デバイセズのエンジニアのみならず、業界で活躍する経験豊富なエンジニアの皆様からも、その解決案や意見などが活発に寄せられました。
ここでは、そのアナログ電子回路コミュニティに寄せられた多くのスレッドの中から、反響の大きかったスレッドを編集し、技術記事という形で公開しています。アナログ電子回路コミュニティへのユーザ投稿に関するライセンスは、アナログ電子回路コミュニティの会員登録時に同意いただいておりました、アナログ・デバイセズの「利用規約」ならびに「ADIのコミュニティ・ユーザ・フォーラム利用規約」に則って取り扱われます。
また、英語版ではございますが、アナログ・デバイセズではEngineerZoneというコミュニティサービスを運用しています。こちらのコミュニティでは、アナログ・デバイセズの技術に精通した技術者と交流することで、設計上の困難な課題に関する質問をしたり、豊富な技術情報を参照したりすることが出来ます。こちらも併せてご活用ください。