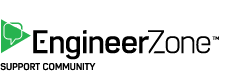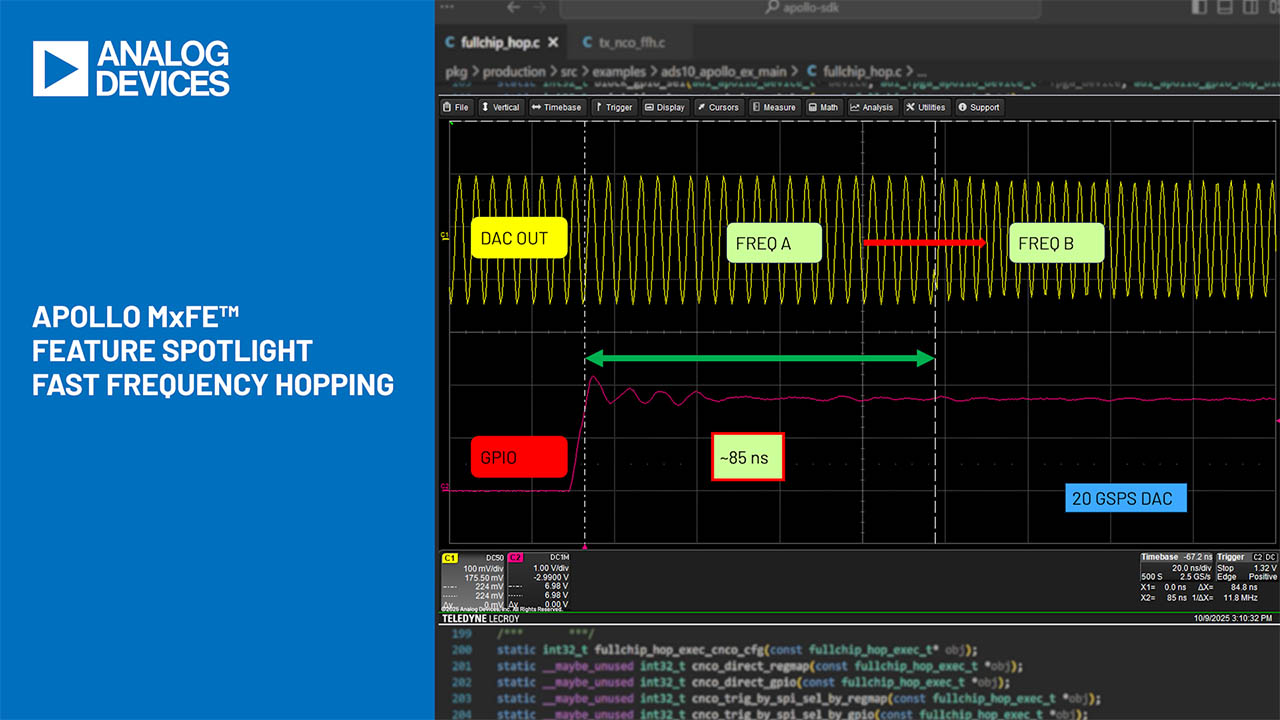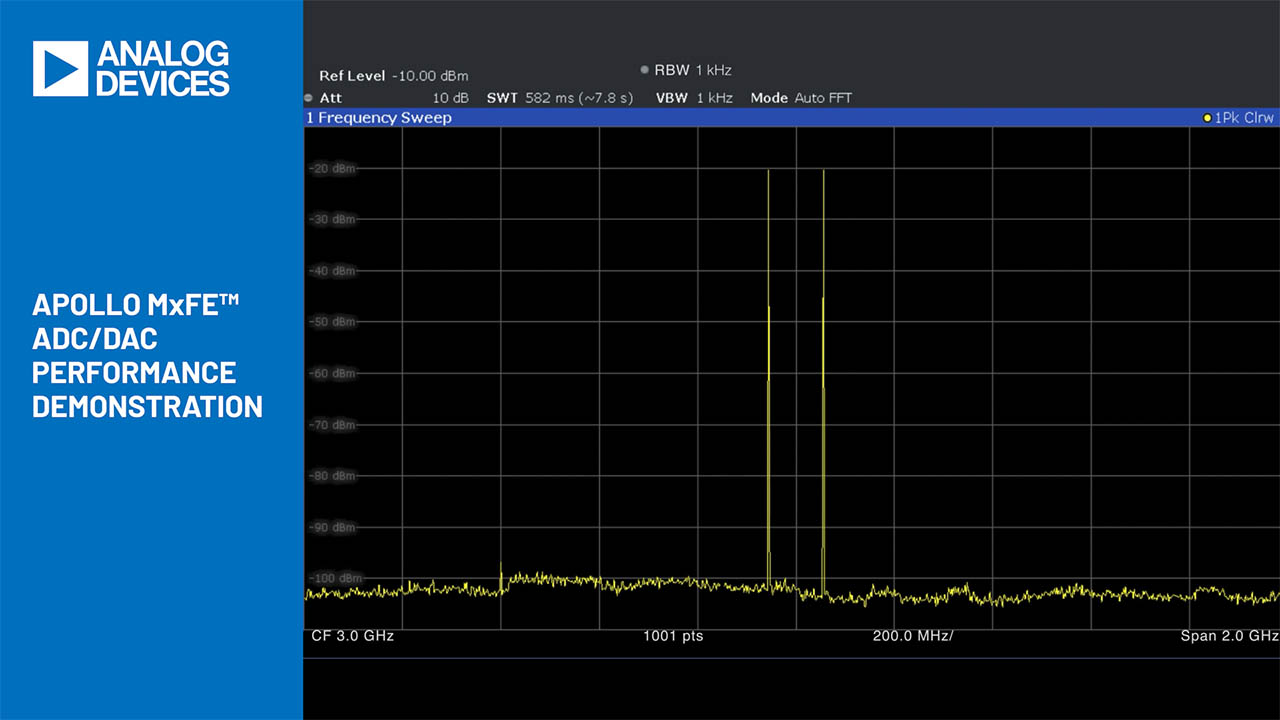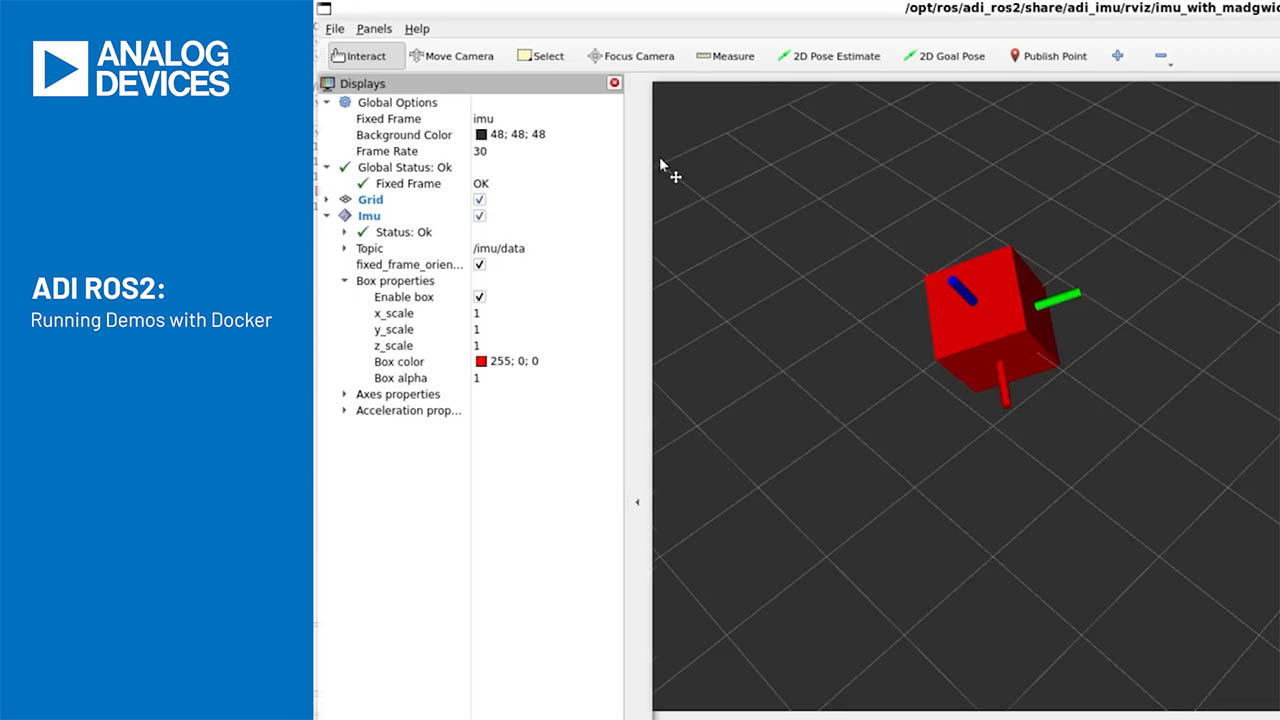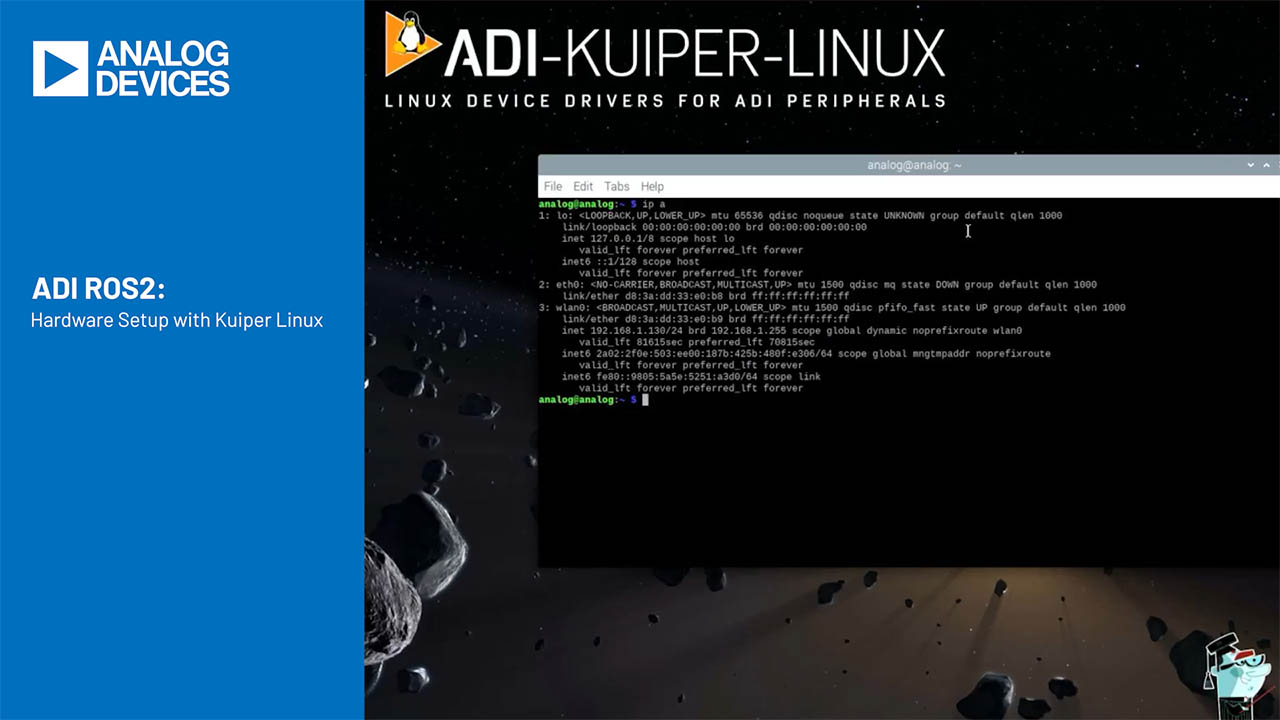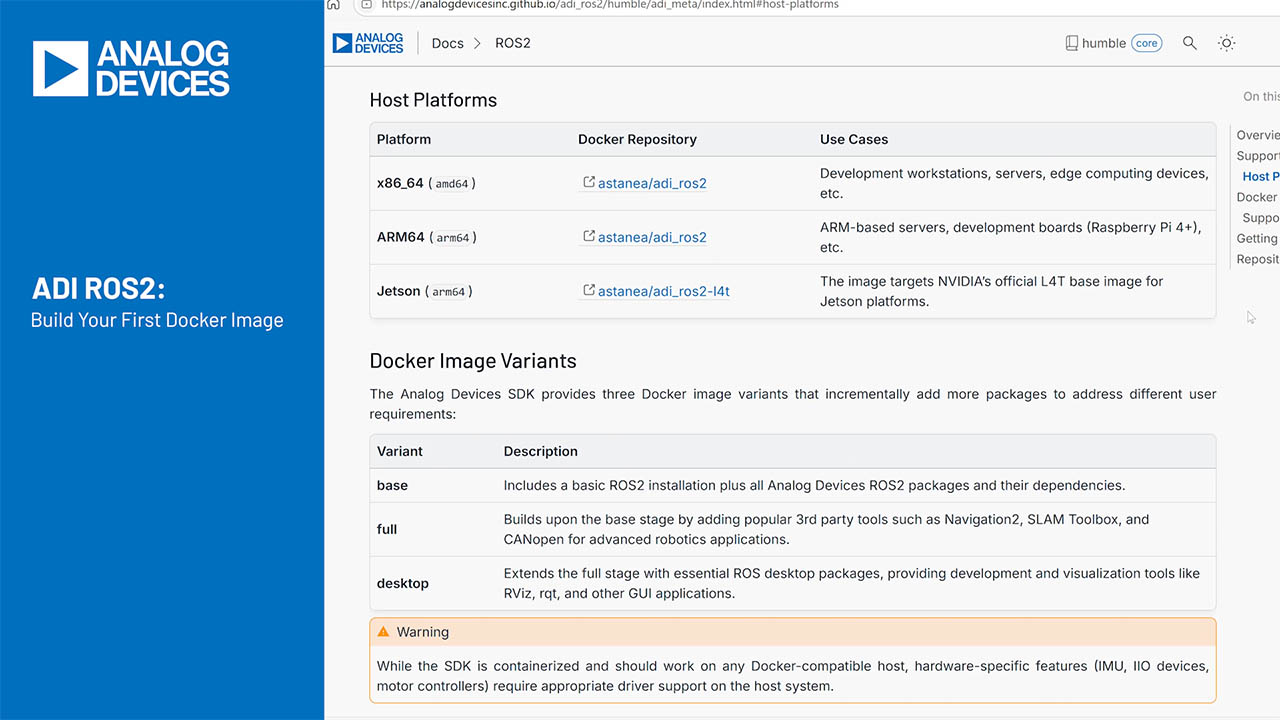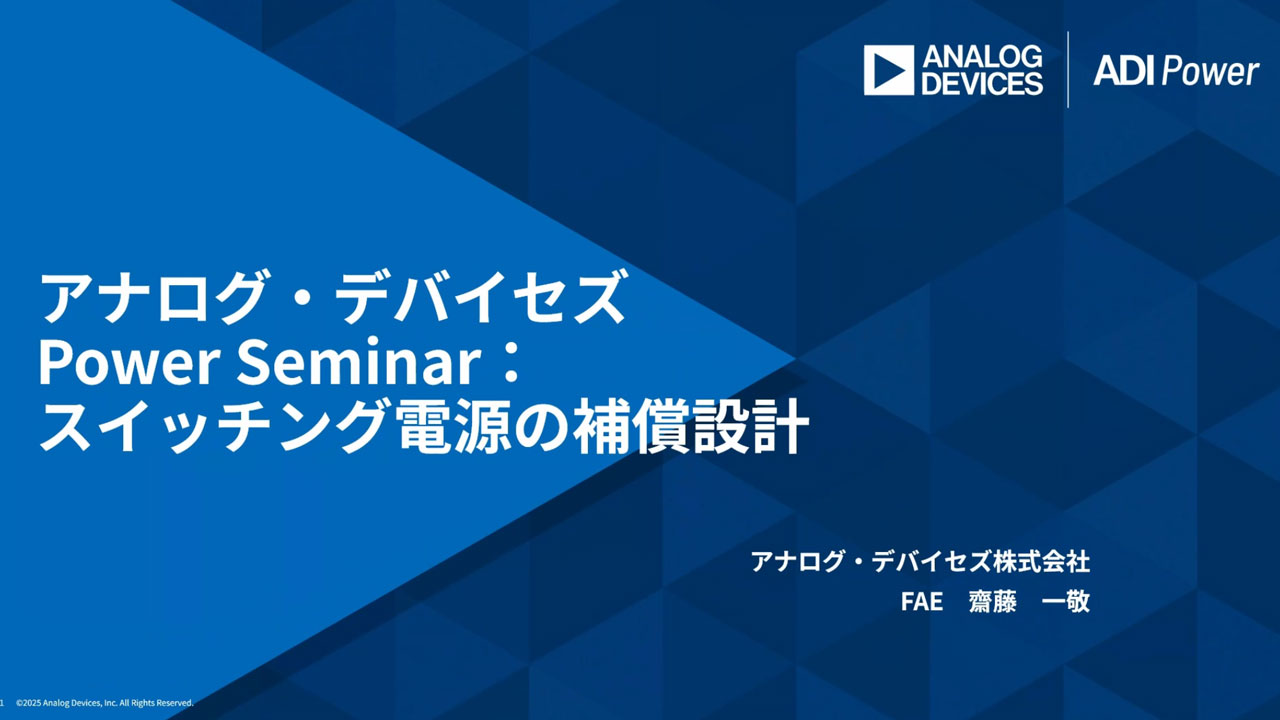電流帰還型のオペアンプでも、トランスインピーダンス回路は構成できるのか?
質問
トランスインピーダンス回路を設計しているのですが、十分な帯域幅が得られず困っています。その対策として、電流帰還型のオペアンプを使うのは可能なのでしょうか?
回答
質問者は、フォトダイオードの電流信号を電圧信号に変換するためにトランスインピーダンス回路を使いたいと考えていました。
フォトダイオードのバイアスは大きく、帰還抵抗は10kΩ程度に設定しました。容量成分を小さく抑えるために、フォトダイオードとしては極めて小さいものを選択しています。数百μAのバイアス電流に重畳した、振幅が数百nAの信号を10MHzの帯域で観測したいと考えているのですが、十分な帯域幅が得られません。
このようなケースの対策として、電流帰還型のオペアンプを使うことはできないのかというのが質問の主旨です。電流帰還型のオペアンプは、一般に電圧帰還型のオペアンプよりも高速(帯域幅が広い)だとされています。そのため、トランスインピーダンス回路の帯域幅の不足を解消することができるのではないかと考えたということです。
ただ、質問者は、電流帰還型のオペアンプの使用には不慣れでした。特に、データシートを見ても、帰還抵抗の値の許容範囲が明確に書かれていないことに困惑したと言います。また、世の中には、電流帰還型のオペアンプを使用したトランスインピーダンス回路に関する情報が非常に少ないことにも気づきました。
確かに、電流帰還型のオペアンプのデータシートを見ると、帰還抵抗の値の許容範囲が記載されていないことが少なくありません。
実際、帰還抵抗については、特定の値が前提となっているケースがほとんどです。言い換えると、それが推奨値として扱われているということです。
例えば、アナログ・デバイセズが提供する電流帰還型のオペアンプ「AD8012」では、データシートにおいて帰還抵抗値は750Ωが前提になっています。また、許容範囲という形での記載は存在しません。
データシートに許容範囲が記載されていないからと言って、帰還抵抗としてどのような値のものでも使用できるというわけではありません。
というよりも、電流帰還型のオペアンプを使用したトランスインピーダンス回路の情報が少ない理由は、オペアンプの仕様に制約が存在するからだと考えられます。つまり、値の大きい帰還抵抗を使用することができず、柔軟性に欠けることがその原因でしょう。
トランスインピーダンス回路、つまりはI-V変換(電流‐電圧変換)回路のS/N比を高めるには、初段のオペアンプにおいて、値の大きい抵抗で増幅(I-V変換)を行う必要があります。
初段での増幅(I-V変換)はわずかに抑え、後段で大きく増幅するというやり方ではノイズ特性が劣化してしまうのです。
参考情報として、ここでは電圧帰還型のオペアンプ「ADA4627-1」を使ったシミュレーション結果を示しておきます。図1では1MΩの帰還抵抗を使用しています。一方、図2では100kΩの帰還抵抗を使用するとともに、ゲインが10の理想アンプを追加しています。図3のノイズ・スペクトラムにおいて、緑色の曲線は図1に対応し、赤色の曲線は図2に対応しています。



ここまでに述べたように、電流帰還型のオペアンプを使うときには帰還抵抗の値に注意する必要があります。また、トランスインピーダンス回路では、初段のアンプにおいて、できるだけ大きな抵抗で増幅をかけるべきだということも事実です。
ただ、電流帰還型のオペアンプを反転増幅器として使うこと自体は、原理的にも実用的にも問題はありません。反転増幅器だけでなく、非反転増幅器を構成することも可能です。電圧帰還型のオペアンプとは異なり、電流帰還型のオペアンプではTIM歪み(Transient Intermodulation Distortion)が生じません。このことが最大の魅力です。
例えば、パルスを入力しても原理的に線形性が保たれます。電流帰還型のオペアンプのゲイン帯域幅積は帰還抵抗に依存します。そのため、帰還抵抗を10kΩに設定すると性能が低下します。帰還抵抗には最適値があり、ほとんどの電流帰還型オペアンプでは680Ω~1kΩ程度のときに最高の性能が得られるはずです。そのため、この範囲の値がデータシート上では推奨されているということです。
最後に、電流帰還型のオペアンプを使用したトランスインピーダンス回路についての参考資料を紹介しておきます。
1つは「OPアンプの歴史と回路技術の基礎知識――OPアンプ大全」という書籍です。これは米アナログ・デバイセズの著作物を日本語に翻訳したものです。その247ページには、図6-18として電流帰還型オペアンプの例が掲載されています。こちらをぜひご参照ください。
また、回路の動作解析などについては以下の資料も参考になるでしょう(一部、上記の書籍の内容と重複している部分もあります)。
MT-034の4ページ目には以下の記載があります。
「Gain is manipulated in a CFB op amp application by choosing the correct feedback resistor for the device (R2), and then selecting the bottom resistor (R1) to yield the desired closed loop gain(電流帰還型のオペアンプ・アプリケーションにおいて、ゲインは、デバイスにとって適切な帰還抵抗R2を選択することによって決まります。また、R1は、望ましいクローズドループ・ゲインの決定に影響を及ぼします).」
一方、MT-057の3ページ目には以下の記述があります。
「Because the closed-loop bandwidth is inversely proportional to the external feedback resistor, R2(クローズドループの帯域幅は、外付けの帰還抵抗R2の値に反比例します).」
上記の内容からもわかるように、周波数特性と安定度をシミュレーションや実測で確認すれば、トランスインピーダンス回路で電流帰還型オペアンプを使用するための適切な帰還抵抗の値が必ず見つかるはずです。
アナログ電子回路コミュニティとは
アナログ電子回路コミュニティは、アナログ・デバイセズが技術者同士の交流のために提供していた掲示板サイトで、2018年3月に諸般の事情からサービスを終了しました。
アナログ電子回路コミュニティには日々の回路設計活動での課題や疑問などが多く寄せられ、アナログ・デバイセズのエンジニアのみならず、業界で活躍する経験豊富なエンジニアの皆様からも、その解決案や意見などが活発に寄せられました。
ここでは、そのアナログ電子回路コミュニティに寄せられた多くのスレッドの中から、反響の大きかったスレッドを編集し、技術記事という形で公開しています。アナログ電子回路コミュニティへのユーザ投稿に関するライセンスは、アナログ電子回路コミュニティの会員登録時に同意いただいておりました、アナログ・デバイセズの「利用規約」ならびに「ADIのコミュニティ・ユーザ・フォーラム利用規約」に則って取り扱われます。
また、英語版ではございますが、アナログ・デバイセズではEngineerZoneというコミュニティサービスを運用しています。こちらのコミュニティでは、アナログ・デバイセズの技術に精通した技術者と交流することで、設計上の困難な課題に関する質問をしたり、豊富な技術情報を参照したりすることが出来ます。こちらも併せてご活用ください。