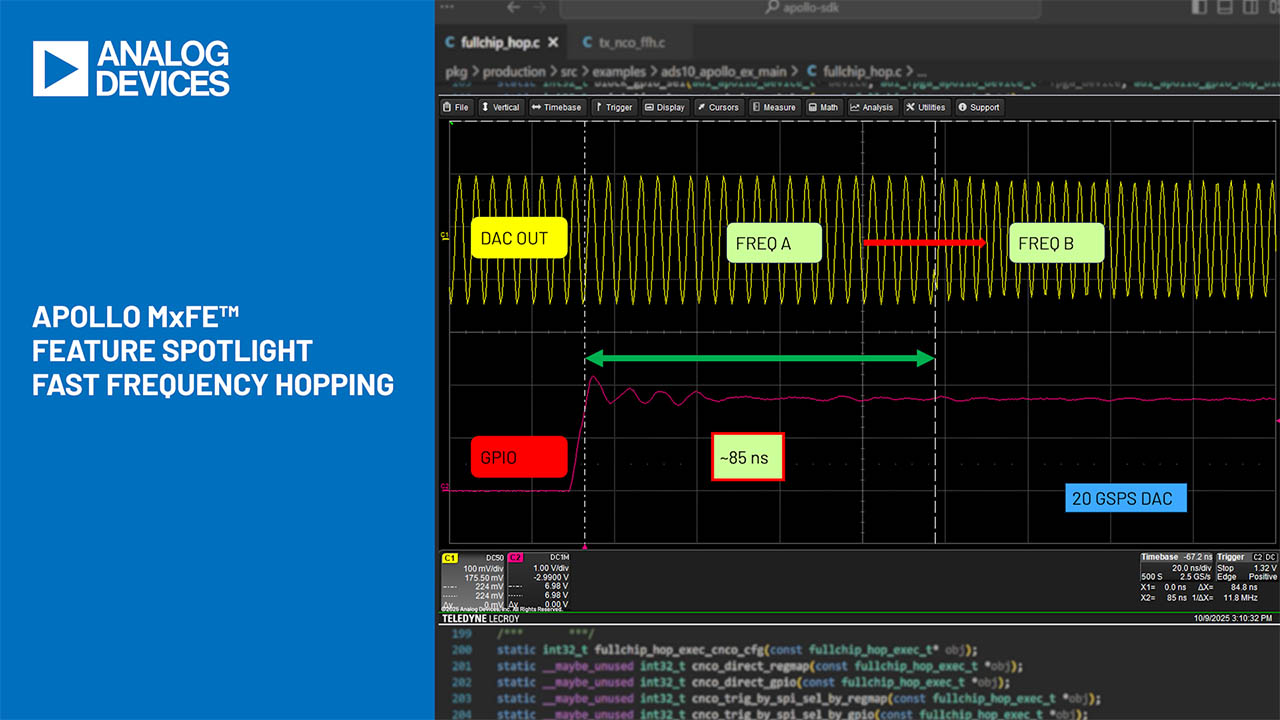要約
無線システムの設計過程は複雑で、多くの場合、プロジェクトに関する多数のトレードオフを伴います。いくらかの洞察と、これらのさまざまな特性のバランスを取ることによって、無線システムの設計作業は容易になります。このチュートリアルでは、これらのトレードオフについて解説し、さまざまな無線アプリケーションで考慮すべき詳細を示します。産業、科学、医療用(ISM)周波数帯を対象として、周波数の選択、一方向システムと双方向システム、変調方式、コスト、アンテナの選択肢、電源の影響、到達範囲への影響、およびプロトコルの選択という主題について解説します。
同様の記事が2012年12月21日に「Electronic Design」に掲載されました。
適切な周波数の選択
なぜ設計者はスペクトル中の433.92MHzの部分ではなく868MHz/915MHz帯で動作させたいと考えるのでしょうか?言い換えると、使用する周波数をどのように選択するのでしょう?その答えは、アプリケーションの動作にとって伝統的な、および/またはあらかじめ定義された帯域が存在するか、それとも設計者が設計に含まれる各パラメータ間でトレードオフのバランスを考えて最適な帯域を選択する必要があるか(図1)という、2つの主な検討事項に影響されます。
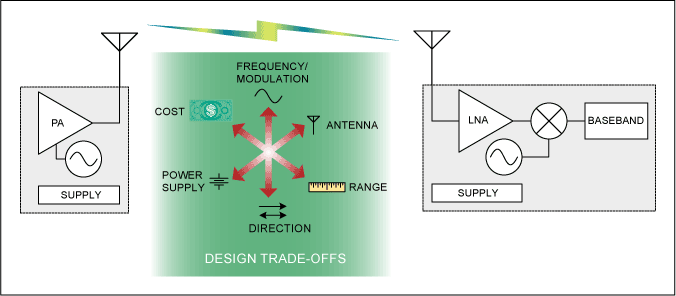
図1. 一般的な無線設計のトレードオフ。
一般的に、新しい設計の最も重要なパラメータは、システムが目標とする到達範囲に適合することです。アプリケーションにアンテナの大きさや配置の制約がなく、無線装置間の距離に障害物がなく、装置がライン電源に接続されている場合は、「どの帯域がより良い選択肢か」に対する答えは簡単に出るでしょう。しかし、民生機器のアプリケーションで、アンテナを露出させることができず、信号が家庭内の壁を通過する必要があり、ボタン電池で数年間システムが動作する必要がある場合は、これらのトレードオフの重要性が増大します。
一般に、低い周波数帯ほど到達範囲が長くなり、見通し(LOS)通信への依存性が小さくなりますが、実際にはその他の影響によって、最終的にシステムで得られる到達範囲がほぼ決定する傾向があります。アンテナの大きさと放射パターン、真の動作環境(障害物が少ない場合とワーストケースの想定)、およびアプリケーションの周囲からのノイズの影響などのパラメータが、通常はシステムの実際の到達範囲に最も大きく影響します。
これらの帯域での出力はどうでしょう?それによって到達範囲や高調波などの面がどのように制限されるでしょう?トランスミッタの出力は、システムの他の欠点を補う上で役立ちます。しかし、これは規制当局によって課せられる制限とのバランスを考える必要があります。アンテナおよび整合システムでの損失と非効率性を埋め合わせるために、トランスミッタを限界まで高出力にするのが最も一般的です。
RKEシステムにおける伝搬損失についてさらに詳しく調べるには、アプリケーションノート3945 「リモートキーレスエントリシステムにおける伝搬損失」を参照してください。システムの到達範囲(リンクバジェット)の見積りと計画に役立てるために、アプリケーションノート5142 「Radio Link-Budget Calculations for ISM-RF Products」およびそれに関連するリンクバジェットのスプレッドシートを参照してください。
一方向システムと双方向システム
一方向通信システムのみを必要とするアプリケーションは、今でも幅広く存在します。たとえば、車のドアロックの解除や、家の窓のブラインドを開けるなどの操作は、いかなる形でも無線でのフィードバックを必要としません。そのため、単純な、コスト効率の良い、一方向の無線通信に対するニーズは常に存在します。
一方向形式の通信の市場は常に存在するでしょうが、監視、フィードバック、ステータス表示、その他のユーザー操作に対するニーズは増大しています。そのため、一方向システムは完全なトランシーバ構成に向かう可能性があります。たとえば、リモートキーレスエントリシステムの場合、ユーザーは車がロックされたことを確認したいと思うでしょう。あるいは、家の窓のブラインドを調整する場合、ユーザーは窓辺の気温を知りたいと思うかも知れません。これらは、どちらも単純な一方向技術が双方向アプリケーションに移行する可能性を示す例です。
変調
ISM帯には、選択可能な多数の変調形式が存在します。使いやすさおよびハードウェアが低コストになる場合が多いため、設計者はローバンド(IEEE® UHF帯の470MHz以下の部分)ではASKを選択する傾向があります。もう1つの方式として、タイヤ空気圧監視システム(TPMS)アプリケーションでFSKがローバンドで使用され始めています。アプリケーション環境の有害な影響(ホイールに装着されて回転するタイヤは振幅変調(AM)を引き起こす傾向が強い)に対する耐性が高いことが分かったためです。あらゆる形式のAMは線形復調方式を使用するため、大量のノイズがシステムを通過するのに対し、FMシステムはより優れた信号対ノイズ比(SN比)とより広い変調(標準FMチャネル上で200kHz)を備えています。しかし、FMは特定の感度スレッショルドを下回ると急速に搬送波へのロックを失います(ウォーターフォール)。
より厳格な規制仕様に適合する必要があるため、FSKはハイバンド(IEEE UHF帯の470MHz以上の部分)でより顕著に使用されています。周波数に基づく変調形式を使用することにより、トランスミッタをCW信号として動作させることが可能になり、PAのオン/オフによって(ASKまたはOOKで)発生するキック作用が抑制されます。さらに高い周波数帯域(1GHz以上、一般的にはIEEEの定義によるLバンド、Sバンド、およびCバンド)では、より高度な変調方式が使用される傾向があります。これは主としてそれらの周波数帯が非常に混雑しており、したがってさらに強力な同一チャネル干渉除去が必要となるためです。
コスト
ISM無線システムの設計におけるもう1つの推進要因は、低コストでありながら高信頼性の動作の必要性です。マキシムのISM無線のポートフォリオのほとんどは、少数の周辺部品で動作し比較的小さいフットプリントを備えた小型の集積デバイスを提供しています。利用可能なトランスミッタの多くは非常に単純なもので、データを送信するための基本的なインタフェース以外には、わずかなインピーダンス整合部品と一般的なデカップリングコンデンサのみを必要とする低ピン数の回路になっています。同様に、レシーバは部品表(BOM)の部品数を低く抑えながらも、システム設計者が特定のアプリケーションのニーズに応じた調整を行うことができる十分な柔軟性を実現する製品が多くなっています。ICの実装面積が小さく、BOMが少なく、2層以上の積層も特に必要ないため、プリント基板(PCB)のコストが低下します。ボードおよび周辺部品のコスト以外に必要な外付け部品は、アンテナとバッテリのみです(非ライン電源システムの場合)。
アンテナ
タイプ、サイズ、形状、方向など、アンテナの物理的特性はシステムの設計と有効性に大きく影響する可能性があります。どのISMアプリケーションでも外形サイズが主要な制約となるため、これらの特性によってどの周波数帯を選択するかが決まる可能性があり、最終的には使用する無線の決定にもつながります。
単純な1/4λモノポールおよび1/2λダイポールから、ループ、F、その他まで、アンテナには多数の形状があります。また、使用する電流モデルの形式によって、電界アンテナと磁場アンテナに分類することもできます。アンテナの設計は、独自の芸術形式とも言えるほどです。アンテナを選択するための第1歩は、アプリケーションの制約の中で許される最大の寸法と、「トレース」を使用するか物理的にアンテナを付加するかを決定することです。表1に、目的の帯域に基づいた関連するアンテナの寸法を示します。
| f (MHz) | λ (m) | λ/4 (cm) | λ/4 on FR4 (cm) | Aperture Size (cm²) | Reactive Near Field (cm) | Far Field (m) |
| 260 | 1.153 | 28.83 | 16.72 | 1058 | 18.35 | 2.31 |
| 300 | 0.9993 | 24.98 | 14.49 | 795 | 15.90 | 2.00 |
| 315 | 0.9517 | 23.79 | 13.80 | 721 | 15.15 | 1.90 |
| 330 | 0.9085 | 22.71 | 13.17 | 657 | 14.46 | 1.82 |
| 434 | 0.6907 | 17.27 | 10.02 | 380 | 10.99 | 1.38 |
| 435 | 0.6892 | 17.23 | 9.99 | 378 | 10.97 | 1.38 |
| 470 | 0.6379 | 15.95 | 9.25 | 324 | 10.15 | 1.28 |
| [868] | 0.3454 | 8.63 | 5.01 | 95 | 5.50 | 0.691 |
| 902 | 0.3324 | 8.31 | 4.82 | 88 | 5.29 | 0.665 |
| 915 | 0.3276 | 8.19 | 4.75 | 85 | 5.21 | 0.655 |
| 928 | 0.3231 | 8.08 | 4.68 | 83 | 5.14 | 0.646 |
FR4上のトレースアンテナは基板の誘電体が原因で0.58だけ「収縮」し、極近接界(Reactive Near Field)はλ/2πとして計算され、遠方界(Far Field)は2λで、開口面積(Aperture Size)は無損失等方性アンテナの場合のλ²/4πです。
表1に基づくと、高い周波数帯ほど小型のアンテナを効率的に使用することができるのは明らかです。しかし、アンテナの物理的サイズが小さくなるほど開口面積も小さくなるため、このプロセスには上限があります。開口面積が小さくなると、アンテナから周囲に対して、およびその逆に転送されるエネルギーが減少します。
アンテナの設計を選択するときは、以下に示す基本的なヒントを忘れないでください。
- 基板の誘電体はトレースアンテナの実効長を短縮します。
- ループアンテナは磁場を生成するのに対し、他の「空中」アンテナは電界を生成します。
- 磁場アンテナ(ループ)は、近接界の環境(リモコン上のユーザーの手など)による影響を受けにくくなります。
- アンテナのグランドプレーン(カウンターポイズ)の長さと方向は放射パターンに大きく影響する可能性があります。
ISMアンテナの詳細な解説については、アプリケーションノート3401 「マキシムの300MHz~450MHzトランスミッタを小型ループアンテナにマッチング」、アプリケーションノート3621 「スモールループアンテナ:パート1-シミュレーションおよび応用理論」、およびアプリケーションノート4302 「300MHz~450MHzトランスミッタ用小型アンテナ」を参照してください。
電源
無線システムに対する給電の手法および電源は、それらを設計に含むアプリケーションの数だけ存在します。一般的な電源には、ACライン電圧、カーバッテリ(12V)と車載5Vバス、リチウムバッテリ(3V)、マルチセルアルカリ電池(1.5V)、充電式電池(1.2V)、エナジーハーベスティング電源、その他が含まれます。ほとんどの場合、トランスミッタとレシーバは別の電源で動作します(TX側はリチウム電池を使用し、RXには車載5Vバスを使用するなど)。これらの構成の場合、最も一般的な電源のトレードオフは、トランスミッタ(またはトランシーバ)のバッテリ寿命とPAの出力の関係です。バッテリに注目すると、非常に効率的なトランスミッタおよびレシーバ回路とともに、規律正しいプロトコルを使用することが推奨されます。バッテリ寿命は、無線回路のスタートアップ時間、マイクロコントローラの使用量、オン/オフのデューティサイクル、PAの効率、使用可能な電圧レベル、レシーバの「待ち受け」電力、および全回路のスリープ電流など、システムのすべての面について考慮する必要があります。
マキシムのISM無線は、市場で最も高効率、低消費電流の製品に含まれます。表2に、ISMトランスミッタの消費電流の概要を示します。
| Part | Mod | 315MHz TX Current (mA) | 434MHz TX Current (mA) | 915MHz TX Current (mA) | Sleep Current (µA) |
| MAX1472 | ASK | 9.1 | 9.6 | — | 0.005 |
| MAX1479 | ASK | 6.7* | 7.3* | — | 0.0002 |
| FSK | 10.5* | 11.4* | — | ||
| MAX7032 | < 12.5* | < 6.7 | — | < 0.8 | |
| MAX7044 | ASK | 7.7† | 8.0† | — | 0.04 |
| MAX7049 | ASK | 16* | 16* | 16*, 27‡ | < 0.35 |
| FSK | 21* | 21* | 21*, 41‡ | ||
| MAX7057 | ASK | 8.1* | 8.5* | — | < 1.0 |
| FSK | 12.2* | 12.4* | — | ||
| MAX7058 | ASK | 8.0* | 8.3* (390MHz) | — | < 1.0 |
| MAX7060 | ASK | 12.5* | 14.2* | — | < 0.05 |
| FSK | 19* | 25* | — | ||
| 3.0V電源レベル、50%デューティサイクルのASK、*は+10dBm時、†は+13dBm時、‡は+15dBm時です。 | |||||
FSKトランスミッタの場合、送信中は信号が「常時オン」になるため(データが信号の周波数によって符号化されるため)、本質的に消費電流が大きくなります。これと対照的に、ASKトランスミッタはPAをオン/オフするため、「オフ」サイクル中はシステムが使用する電流が減少します。電流の供給源となるバッテリを比較すると、消費電流の重要性がより明確になります。各メーカーは、自社のバッテリのサイズ、容量、および使用モデルについての情報を提供しています。一般的なバッテリの情報を表3に示します。
| Battery | Technology | Nom Voltage (V) | Capacity (mAh) | Ø/Thick (mm) | Weight (g) | |
| A27 | Alkaline | 12* | 22 | 8.0/28 | 4.4 | |
| 394 | Silver Oxide | 1.55 | 63 | 9.4/3.5 | 1.1 | |
| A312 | Zinc - Air | 1.4 | 160 | 7.9/0.5 | 3.6 | |
| CR2032 | Lithium | 3.0 | 225 | 20/3.2 | 2.9 | |
| CR2450 | Lithium | 3.0 | 620 | 24.5/5.0 | 6.8 | |
| CR3032 | Lithium | 3.0 | 500 | 30/3.2 | 6.8 | |
| CR2 | Lithium | 3.0 | 850 | 15.6/27.0 | 11 | |
| AAA | Alkaline | 1.5 | 1000 | 10/44 | 11 | |
| AAA | NiCd | 1.2 | 250+ | 10/44 | 9.5 | |
| AAA | NiMH | 1.2 | 550+ | 10.5/44 | 13 | |
| 9V | Alkaline | 9† | 550 | 25.5 x 16.5 x 46 | 46 | |
| AA | Alkaline | 1.5 | 2500 | 14/50 | 23 | |
| AA | NiCd | 1.2 | 600+ | 14/50 | 22.7 | |
| AA | NiMH | 1.2 | 1500+ | 14.5/50 | 26 | |
| CGR18650 | Li-Ion | 3.6 | 2250 | 18.6/65 | 45 | |
| C | Alkaline | 1.5 | 7+ Ah | 25/49 | 70 | |
| D | Alkaline | 1.5 | 16+ Ah | 34/60 | 141 | |
| Automotive | Lead - Acid | 12‡ | 40+ Ah | Various | Various | |
| *ボタンスタック(12セル)、†6セル、‡6セル | ||||||
回路の消費電流を測定する以外に、バッテリ寿命に影響するもう1つの要素として自己放電率があります。ISMアプリケーションで使用されるバッテリの場合、この自己放電率と使用される技術との間に強い関係があります(表4)。
| Technology | Anode | Cathode | Electrolyte | Self-Discharge (%/month) |
| Lithium | Li | MnO2 | LiClO4 | < 0.08 |
| Alkaline | Zn | MnO2 | KOH | < 0.17 |
| Silver Oxide | Zn | Ag2O | NaOH/KOH | < 0.17 |
| Li-ion | LiCoO2 | LiC6 | Li Salt (var) | 2–3 |
| Lead - Acid | PbO2 | PbO2 | H2SO4 | ~ 6 |
| Zinc - Air | Zn | O2 | Zn | ~ 8 (exposed) |
| NiCd | NiOOH | Cd | KOH | 15–20 |
| NiMH | NiOOH | (var) | KOH | ~ 30 |
リチウム(Li+)バッテリは、サイズが小さく長寿命(低自己放電)のため、小型の民生機器用として最も一般的です。バッテリの選択に影響するその他の要因として、ピーク放電率および保存/使用温度があります。これらのバッテリは寿命の大部分にわたって安定した電圧を供給することができますが、どの技術にも電池内の直列抵抗(内部抵抗(IR))が次第に増大することによる電圧低下という問題があります。多くの場合、この低下は無線の最小動作電圧を規定するために使用されます。しかし、リチウムバッテリが公称電圧の90%に達すると、残りの有効電流もその限界に達し始めます。
たとえば、CR2032を200mAh用に使用した場合、一般的に内部抵抗は通常の値である約15Ωから約30Ωへと2倍に増大し、一方で電圧は3.0Vから2.8Vに低下します。通常、バッテリのIRが約50Ωに達して電源レベルが約2.3Vに低下するグラフの屈曲部が225mAh付近に存在します。容量が240mAhに減少した時点で、内部抵抗は120Ω以上になっている可能性があり、通常は電圧が1.8V以下に低下しています。そのため、バッテリ寿命に関して、電圧降下は電流容量の完全な喪失ほど重大な問題にはなりません。
到達範囲
システムの予測到達範囲は多数の要因、特に動作周波数、トランスミッタの出力、アンテナの効率、およびレシーバの感度に大きく依存します。障害物、動き、および大気の状態でさえ動作距離に大きく影響する可能性がありますが、これらはシステム設計者の制御が及ばない変数です。そのため、ワーストケースの環境に対する設計の選択肢は、通常はTX出力、アンテナの選択、およびRX感度に限定されます。
トランスミッタの出力は、システムの到達範囲に最大の影響を与える可能性があります。特に、低い周波数帯では1/4波長以下の寸法によりアンテナ効率が10%以下になる場合があります(キーフォブのサイズ)。アンテナ効率の低さを補うために、しばしば規定値を超えるPAからの出力が使用されます。動作対象の地域におけるすべての規制の要件の範囲内に抑えることが特に重要です。トランスミッタのデューティサイクルが変更可能な場合には、より高い出力が監督機関によって許容される可能性があります。
出力に基づいてPAを選択するときは、以下のことを忘れないでください。
- 出力が大きいほど、より多くの消費電流が必要になります。
- 周波数帯が高いほど、(通常はPLL電流が原因で)より多くの動作電流が必要になります。
- 出力を大きくすると、最大放射電力、占有帯域幅、および高調波出力などの規制の上限に抵触する可能性があります。
表5に、マキシムのISMトランスミッタの能力の概要を示します。
| Part | Bands (MHz) | Typical TX Power (dBm) |
| MAX1472 | 300 to 450 | 10 |
| MAX1479 | 300 to 450 | 10 |
| MAX7032 | 300 to 450 | 10 |
| MAX7044 | 300 to 450 | 13 |
| MAX7049 | 288 to 945 | 15 (adjustable) |
| MAX7057 | 300 to 450 | 10 |
| MAX7058 | 315/390 (300 to 450) | 10 |
| MAX7060 | 280 to 450 | 10, 14* |
| すべての出力仕様は50Ω負荷駆動時のもので、整合/高調波フィルタ損失を含みます。 *5V電源時 |
||
システムのレシーバ側では、実現可能な到達範囲に対して感度が圧倒的な影響力を持ちます。トランスミッタ側と同様に、3dB低い出力の信号を受信可能なレシーバによって、貧弱なアンテナや不十分なリンクの環境を補うことが可能です。
レシーバの感度を選択するときは、以下のことを忘れないでください。
- 一般にレシーバの感度はASK変調の方が高くなります。
- レシーバは通常は低い周波数で高い感度を示します。
- データレートは感度に明確な影響を与え、低速では大幅に数値が良くなります。
表6に、マキシムのISMレシーバの感度の仕様の概要を示します。
| Part | Mod | 315MHz RX Sensitivity (dBm) | 434MHz RX Sensitivity (dBm) |
| MAX1470 | ASK | -115 | -110 |
| MAX1471 | ASK | -116 | -115 |
| FSK | -109 | -108 | |
| MAX1473 | ASK | -118 | -116 |
| MAX7032 | ASK | -114 | -113 |
| FSK | -110 | -107 | |
| MAX7033 | ASK | -118 | -116 |
| MAX7034 | ASK | -114 | -113 |
| MAX7036 | ASK | -109 | -107 |
| MAX7042 | FSK | -107 | -106 |
| 記載されたすべての感度は「平均電力」としての値です。「平均搬送波電力」の場合は3dB低くなり、「ピーク電力」の場合は3dB高くなります。 | |||
プロトコル
アプリケーション用のプロトコルの選択は、アプリケーションによってシステム設計の最終段階の場合と出発点の場合があります。プロトコルは、無線がどのように情報を交換するかを管理するもので、電話通信(アナログ音声)の要件、データ/ビット構造、符号化方式、ハンドシェイク交換手順、および電波を共有するためのネットワーク規約などのパラメータが含まれます。多数の選択可能な標準プロトコルが存在し、独自の通信形式もそれと同様に数多く存在します。通常、プロトコルの選択に最大の影響を与える設計パラメータは、一方向と双方向のどちらのシステムを使用するかということです。異なる無線ノード間での電波のネゴシエーションと衝突防止が必要になるため、双方向システムの方が複雑になる傾向があります。
一般的アプリケーション
各種のアプリケーションは、それぞれの間で共通する要件や制約によって、特定の通信方向、周波数、および変調方式にグループ化する傾向があります。表7に、アプリケーションに基づく標準的な使用モデルの概要と、各アプリケーションで一般的に見られる周波数および変調方式の指針を示します。
| Application | Direct | Frequency | Modulation | Notes | |
| Automotive | Remote keyless entry (RKE) | 1-way | 315MHz, 434MHz | ASK | After-market systems and high-end luxury automobiles are moving toward two-way communication to provide feedback to the user in addition to the RKE function. |
| Passive keyless entry (PKE) | 2-way | 125kHz, 13.56MHz | ASK | — | |
| Tire-pressure monitoring system (TPMS) | 1-way | 315MHz, 434MHz | FSK | — | |
| Garage-door opener (GDO) | 1-way | 315MHz, 390MHz | ASK | The U.S. Military uses 390MHz in certain locations; as such 315MHz is used to cover those areas | |
| Electronic toll collection (ETC) and automatic vehicle identification (AVI) | 1-way | — | — | — | |
| Wireless OBDII | 1-way | 315MHz, 434MHz | ASK | Monitor maintenance conditions, driving habits, etc. | |
| Automatic meter reading (AMR) | Water meter | 1-way | 470MHz, 868MHz, 915MHz | FSK | AMR is a growing field of automation for large utilities and the meter-manufacturing industry. It is a subset of sensor networks (HAN, NAN, mesh network), collector/concentrator structures, etc. |
| Gas meter | 1-way | 868MHz, 915MHz | FSK | — | |
| Electric meter | 2-way | 868MHz, 915MHz | FSK | Occasionally designed as the "collector" for a home area network (HAN) | |
| Home automation (HA) | Wireless remote control | 1-way | 434MHz | ASK, FSK | IR replacement, AV systems, set-top boxes, multiroom controls, wireless data streaming (control channel) |
| Lighting | 1-way | 390MHz, 418MHz, 434MHz | ASK | Mood lighting, coordinated with AV | |
| Motor control | 1-way | 434MHz | ASK | Projector screens, blinds/shades, coordinated with HVAC | |
| Security/fire | 1-way 2-way |
345MHz, 434MHz | ASK | — | |
| GDO | 1-way | 315MHz, 390MHz | ASK | Gate opener, driveway security | |
| Heat allocation | 1-way | — | — | — | |
| Energy management | 2-way | — | — | Programmable thermostats, watt-meter displays | |
| Home weather stations | 1-way | — | — | Remote sensing | |
| RFID | Product tracking | 2-way | 915MHz, 2.45GHz, 5.8GHz | ASK, FSK, BPSK | — |
| Rail trucking | 2-way | 915MHz, 2.45GHz, 5.8GHz | ASK, FSK, BPSK | — | |
| Wireless networking | Bluetooth LE | 2-way | 2.45GHz | FHSS | IEEE 802.15.1 |
| Wi-Fi | 2-way | 2.45GHz, 5GHz | DSSS, FHSS, OFDM | IEEE 802.11 | |
| Wildlife tracking | Land/aquatic/air | 1-way | 410MHz | PSK | ARGOS satellite system |
トレードオフ
個々のアプリケーション、市場、および設計は異なるため、それぞれ異なる優先順位があります。表8に、ISM無線システムの設計者が遭遇するさまざまなトレードオフの概要と、動作周波数帯および変調方式の指針を示します。
| Priority | Band | Modulation | Reasoning | Tradeoffs |
| Range | Lower, mid | ASK | Assuming a large antenna, lower frequencies allow for better RX sensitivity. ASK commonly has better RX sensitivity than FSK. Midband regulation allows for more radiated TX power. | Cost, battery life, size, simplicity, DR, IR |
| Cost | Lower | ASK | Small and simple circuits. ASK is a preferred modulation for a simple TX. ASK RX chips tend to require the fewest peripheral components. | Range, battery life, DR, IR, tolerance |
| Battery life | Lower | ASK | Lower current drain at lower operating frequencies for both the TX and RX provide longer life from a limited source. ASK only requires a duty cycle % versus constant transmissions for FSK. | Range, cost, LOS, simplicity, DR, IR |
| Size | Mid | — | If size includes the antenna, then the 868MHz/915MHz bands are the best target because small antennas can be used with reasonable aperture sizes and electrical lengths. If there is no restriction on the antenna, then refer to the "Cost" priority. | Range, LOS |
| Line-of-sight (LOS)/obstacles | Lower | FSK | Lower frequencies penetrate obstacles, bend around objects more easily, and suffer less absorption than higher frequencies. FSK is less influenced by multipath and possible amplitude changes caused by motion (TPMS example). | Battery life, size |
| Simplicity | Lower | ASK | ASK is an easier and more tolerant modulation scheme to handle. Larger wavelengths (lower frequencies) are less influenced by board and component sizes. | Range, battery life, DR, IR, tolerance |
| Data rate (DR) | Higher | FSK, PSK spread spectrum | Higher data rates will require wider bandwidths for operation and the regulatory requirements are easier in the higher bands. High data rate, spread spectrum, and the high bands all require more operating current. Smaller aperture and wider bandwidth negatively impacts the range. | Range, cost, battery life, simplicity |
| Interference rejection (IR) | Mid, Higher | Spread spectrum | Spread-spectrum modulation rejects carriers and other interference very well. The wider bandwidths needed for operation are available in the higher bands. | Range, cost, battery life, simplicity |
| Frequency tolerance | Lower | — | More important at higher bands. Narrower IF filters will provide better sensitivity and longer range. Absolute frequency accuracy is easier to obtain at lower bands. TCXOs are more expensive than standard crystals. | Cost, simplicity |
ガイドライン
マキシムが提供するすべてのISM無線製品は、優れた標準アプリケーション回路が製品のデータシートに含まれています。これらの回路は、システムの設計を開始するための優れた出発点を提供します。トランスミッタの回路図を作成するとき、通常は他に必要な部品は、マイクロコントローラまたは簡単なエンコーダインタフェース、アンテナ整合回路、および何らかの電源のみです。レシーバの場合は、マイクロコントローラまたはデコーダインタフェースと電源システムの他に、目的の周波数およびデータレート用に調整されたいくつかの回路を構成する必要があります。回路図の完成後は、RFシステムで遭遇する設計上の問題のほとんどが不適切なPCBレイアウトに起因するということを忘れないでください。PCBレイアウトで避けるべき最も一般的な重大問題について調べておくと、システム開発のテストおよびデバッグフェーズにおいて一定の時間を節約することができます。詳細については、チュートリアル4636 「Avoid PC-Layout “Gotchas” in ISM-RF Products」および5100 「RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン」を参照してください。
マキシムのISMトランスミッタについては、必ず以下のアプリケーションノートをお読みください。
アプリケーションノート1954 「Designing Output-Matching Networks for the MAX1472 ASK Transmitter」
アプリケーションノート3401 「マキシムの300MHz~450MHzトランスミッタを小型ループアンテナにマッチング」
マキシムのISMレシーバについては、以下のアプリケーションノートを参照してください。
アプリケーションノート1017 「MAX1470スーパーヘテロダインレシーバ用の水晶発振器の選び方」
アプリケーションノート1830 「How to Tune and Antenna Match the MAX1470 Circuit」
アプリケーションノート3671 「UHF ASKレシーバ用のデータスライス手法」
この記事に関して
製品
315MHz/434MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
315MHz/390MHzデュアル周波数ASKトランスミッタ
300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
IFフィルタ内蔵、300MHz~450MHz ASKレシーバ
高性能、288MHz~945MHz ASK/FSK ISMトランスミッタ
308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz、低電力、FSKスーパヘテロダインレシーバ
300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ
315MHz/434MHz低電力、3V/5V ASK/FSKスーパーヘテロダインレシーバ
300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ
280MHz~450MHzプログラマブルASK/FSKトランスミッタ
315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
300MHz~450MHz周波数設定可能なASK/FSKトランスミッタ
AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ
フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ