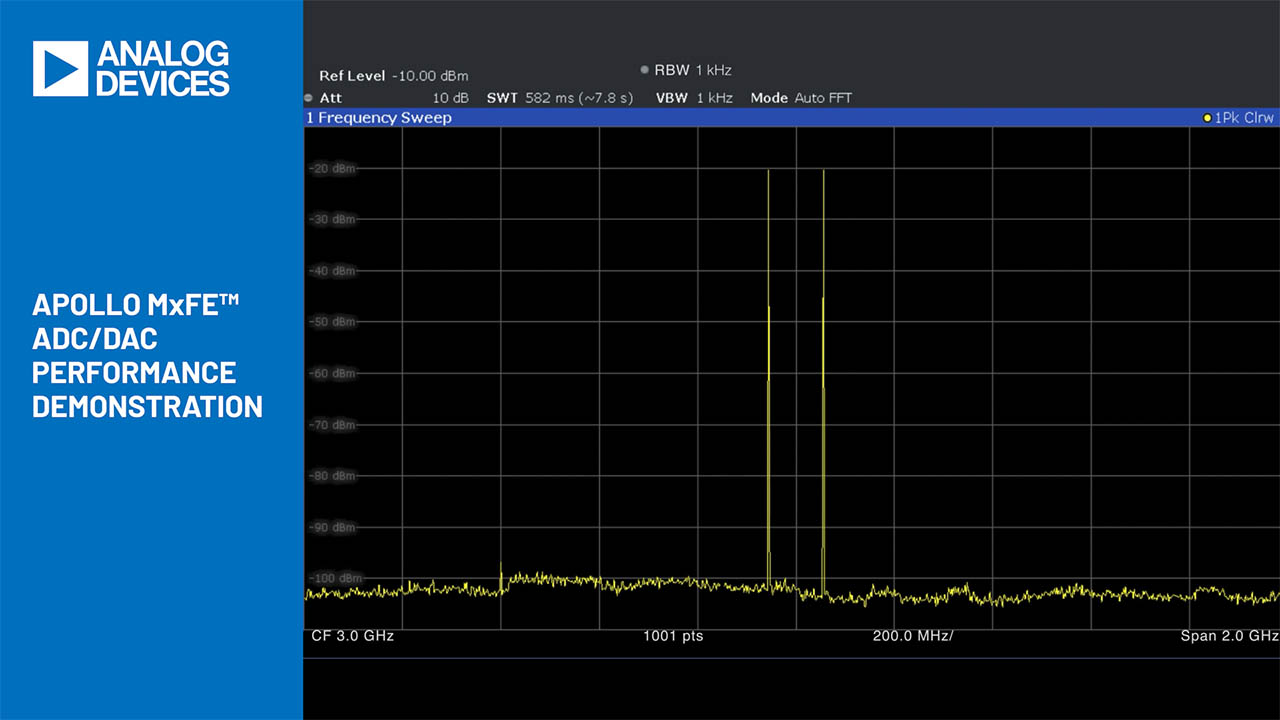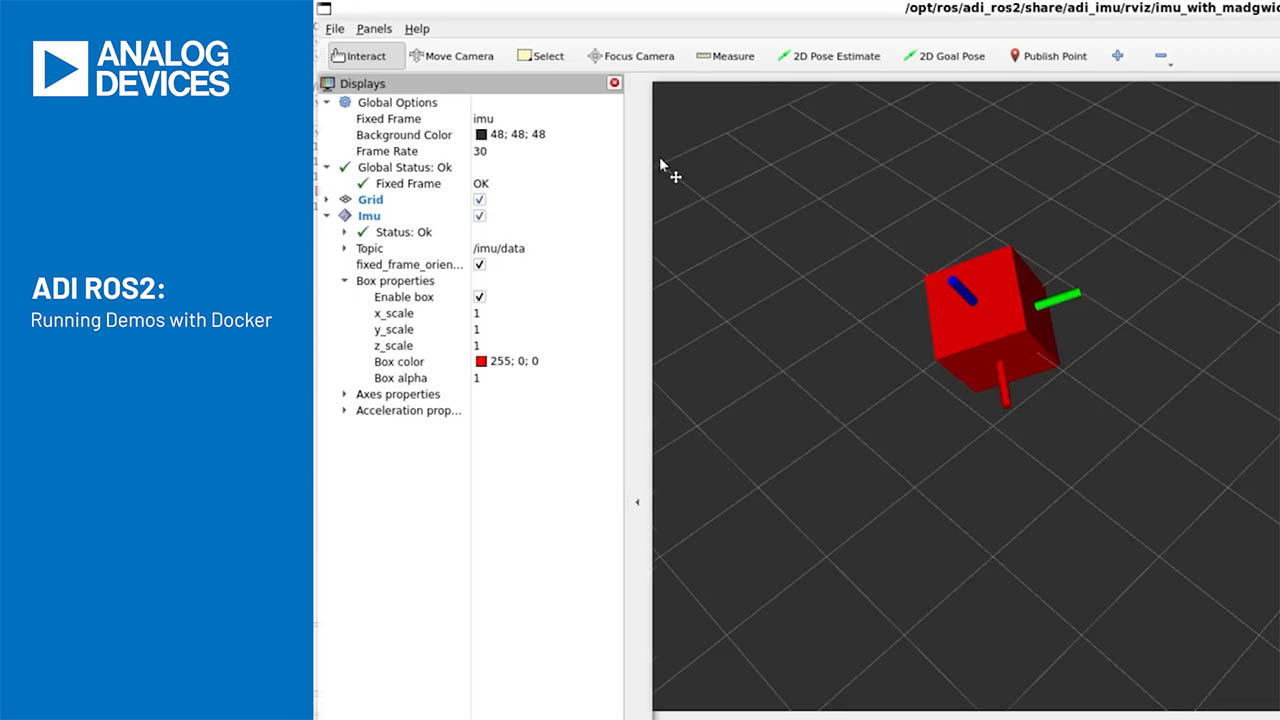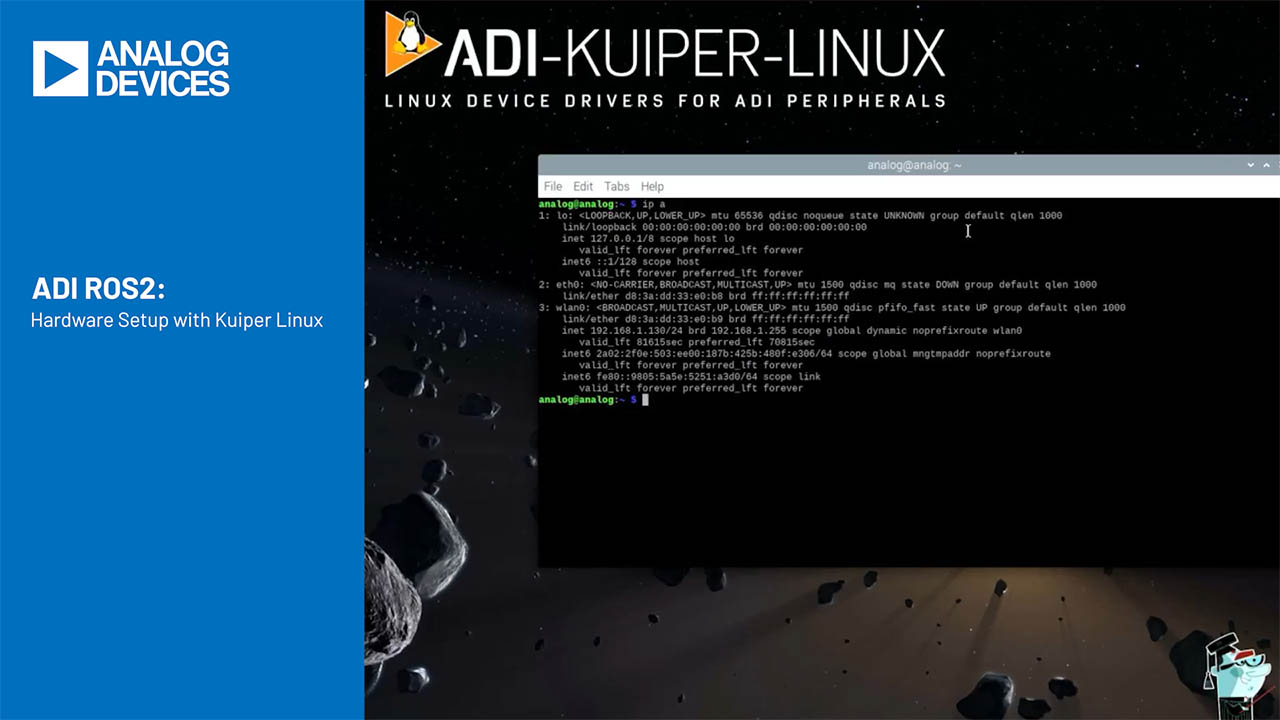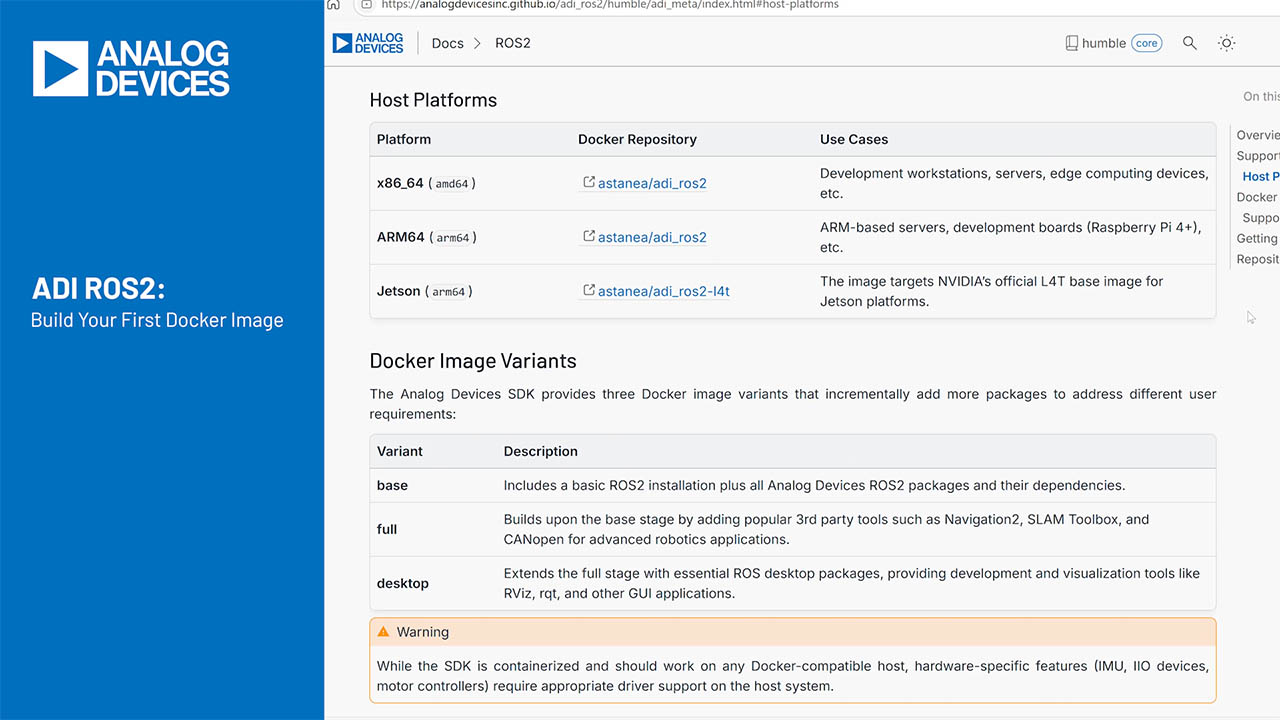ここで紹介する内容は、前に US の ADI 社エンジニアが講演した内容について、別に直接教えてもらったことを日本語にしています。
アンプ回路の基本的な動作に関する解説なので、現在の OP アンプ回路においても全く同じことが応用できます。OPアンプなどのリニア回路では、差動トランジスタのペアが入力段となり、その後ろに増幅段が連なっています。バイポーラ・トランジスタで構成された差動入力段を持つOPアンプ回路の歪み特性に付いて、その回路アーキテクチャから解析しています。これを読むと、歪み特性に関する電圧フィードバック・アンプ型 OP アンプの基本的な弱点が見えてきます。
一般的にわれわれが知っていることは、信号周波数が高くなると OP アンプの高調波歪み(Distortion)が大きくなるということです。ですからこの特性が重要な時は、OP アンプを使う時は、信号に比べて帯域が広いアンプを選んでいます。一般的な電圧帰還型 OPアンプは、基本的に積分器としての動作をしています。内部ブロックとしては、入力差動ペアによる gm 段(トランスインピーダンス段)とそれにつづく増幅段ですが、この増幅段には容量Cが含まれこれが積分器としての特性を決めています(図1)。この容量は、ジャンクション容量であったり、メタル配線による容量であったりします。下段の C の接続先は、一般的にグランドではなくマイナス電源です。

この gm 段と増幅段をもうすこし詳しくしたものが、図 2 です。入力の差動バイポーラ・トランジスタのペアが gm 段です。テール電流 I は、このペアトラに加わる電圧により差動で比率が分割されます。この回路のユニティゲイン帯域は、積分器のC と gm の値により決まります。
ペアトラは、加えられた差動電圧により差電流を発生します。ここでこのトランジスタ・ペアに加わる差動電圧⊿V とその出力である差動電流の関係を見ると、図 3、および図 4 のようになります。入力⊿V と差電流⊿I の関係は、図 3 のように tanh の関数で表され、その変化率、すなわち gm は、図 4 のように sech の二乗関数で表されます。いずれも双曲線関数となります。実際のトランジスタでは、gm のピークである⊿V=0V からほんの数10mV離れただけで、gm が大幅に低下します。差動ペア全体の電流は、図 6 のように I なので、出力電流はこれ以上にはなりません。(-1<X<+1)FET は、バイポーラに比べてこの gm 特性が緩やかなので(その代わりピークが低いのでゲインが低い)、低周波数での歪みを気にするオーディオアンプなどのアプリケーションで使われることがあります。

ここで横軸は差動入力段の電圧差、縦軸はペアに流れる電流の差になります。

gm は、sech の二乗の関数となり、⊿V が0V を中心とした狭い範囲で大きな値を持ちます。

ここで、もうすこし差動ペア段に注目すると、トランス・インピーダンス gm は、つぎのように近似することができます。

もし⊿V が小さい範囲であれば、次の式が成り立ちます。

この考えを前提にしてこれからアンプの歪みについて計算しようとしています。このアーキテクチャによるアンプの Distortion がどれぐらい存在する可能性があるのかを、検討してゆきます。

ここで先に出てきた電圧帰還型OPアンプのブロック図に戻ります。(図 6)ここでは入力差動ペアに対してサイン波を信号として与えています。この構成のアンプは、積分器として動作するので、出力信号と積分器の C に流れる電流信号は、90度位相のずれた信号です。

ここで入力 Vi=Vo+⊿V です。⊿V と C に流れる電流 I は次のように表されます。

ここで上のまん中の式を展開すると、

となるので、これを利用して⊿V の近似式を求めます。

ここで

であるので、これを使い上の式を変形すると、

となります。 3 次高調波による Distortion は、その注目する周波数ωにおける一次の項と三次の項の比率になります。

ここで実際のアンプで、どれぐらい歪みが現れるか計算してみます。
少し以前に一般的だった、汎用 OP アンプを例として考えます。次の条件を例とします。
ω1=2π・1 MHz, (Unity Gain BW) ω=2π・20 KHz, (信号周波数), E=10V, VT=0.026V
この時の歪みは、

という大きな値なります。また入力と出力の位相差は、次のようになります。

この最後の式の意味は、信号の振幅が増えると位相ずれが増えることを意味していて、振幅の変化(AM)が位相の変化(PM)による歪みを生じさせていることになります。また仮に信号振幅が同じだったとしても、その周波数が異なれば、やはり位相が変調されてしまいます。しかもこの位相ずれθは、周波数に大してリニアではありません。それぞれ図 7 を参照してください。

これが、電圧帰還型 OP アンプの大きな弱点のひとつです。gm 段に伝達特性が異なる FET を使用することもひとつの方策ですが、その場合 gm 自身は、バイポーラ・タイプよりずっと小さくなり、ゲインが下がってしまいます。お互いの良いとこ取りをしようと、入力 gm 段に FET とバイポーラ・トランジスタをパラレルに接続したバトラーアンプというものも考え出されていますが、根本的解決ではありません。次に改善策のいくつかを、 解説したいと思います。
前段までに、一般的なバイポーラの入力ペアを持つアンプの gm 段の動作特性による制限から、このタイプの電圧フィードバック型アンプにおける信号の歪み(Distortion)の増加ということを説明しました。これはバイポーラペアがもつgmの伝送特性が、sech(双曲線関数)特性を持ち、大きいgmの範囲が狭い入力電圧に限られることと、電圧帰還オペアンプの内部回路が、基本的にgm段+積分器で構成されていることに原因がありました。入力信号の周波数や振幅が変わることにより、入力と出力の位相差がモジュレーションされ、歪みの補正を難しくしていました。

この形のオペアンプには、この歪み特性以外に高速のステップ信号を扱おうとした場合、次のような弱点があります。 図 8 のように入力にステップ信号が加わると、仮想グランドでの動作を期待していても、アンプ出力がセトリングするまではこの状態からはずれ加算ノードはオープン状態となり、内部の電流ソースは飽和状態となります。

図 9 のように入力にダイオードクランプをつければ、電流ソースが飽和することはありませんが、スルーレートが制限されます。このスルーレートの問題は、この回路構成での原理的な問題です。gm段の改善によりこの問題を小さくすることはできますが、なくすことはできません。
ここで広帯域アンプのトポロジーとしてよく知られているトランス・インピーダンス・アンプ(電流フィードバック・アンプ)について考えてみます。(図 10 参照)ご存知のように、このアンプは電圧フィードバック・アンプに似た周辺回路で動作しますが、動作原理が異なり、ゲインはインピーダンスの次元を持ちます。(図 11 参照)
ここでこの回路の動作特性に付いて、特に帯域に関して検討してゆきます。前の図によれば出力 VOUT は、入力電流 IIN と出力段手前のインピーダンス ZT を用いて図 11 の下の式ように表され、その時のゲインは DC と AC でそれぞれその下に示される式になります。



ここでこのアンプ回路に図 12 のように R1、R2 というフィードバック回路をつけるとその特性は、次のようになります。


AC 的には、よく知られているようにドミナントポールは、内部回路により決まります。また R1 は、帯域を制限する要因ではなくなります。このようにトランスインピーダンス・アンプは、低ひずみで広帯域の優れた特性を持つアンプですが、やはりオールマイティーではありません。このアンプはその動作特性から、次のようなプリケーションに向いています。
* 電流・電圧変換回路
* 反転アンプ回路での最適動作。
* 低歪み、高速動作
* 回路のトポロジーとしてはスルーレートの制限がない。
しかしながらその代償として、次のような癖も有しています。
* 反転・非反転入力は、同一特性ではなく、片側が HiZ、もうひとつが LoZ となります。
* “I”入力のノード(反転入力ノード)では大きなオフセット電流が生じます。
* 反転ノードでの大きな電流ノイズ発生。
これらの問題を解決し、前号で解析した入力バイポーラペアにおける gmの tanh特性に起因する歪み特性を改善する回路方式として、次に説明するアクティブフィードバック・アンプを取り上げます。(図 13 参照)このアンプは、バイポーラ差動ペア(FET を使用しても可能)をふたつ入力段に組み込むことで、gmの tanh 特性のリニアリティを補正し、そこで発生する歪み成分を最少に抑えることを狙った回路です。時々誤解されることですが、このアンプは計装アンプではありません。

ここで入力段の G は、入力信号の振幅が大きい時の gm を表します。ふたつの入力は、回路特性が全く同じものを使用します。この gm 段は図 14 のように、等価なバイポーラペアがふたつ並列に接続されたもので、電圧・電流の変換と特性が同じであれば、適切なフィードバックをかけることにより、お互いの tanh 特性を補正しあうことになり、良好なリニアリティを得ることが可能です。実際の回路では、このふたつの gm 段と出力アンプの間には、このペアのためのバイアス電流を供給するための、コモンベースのフォロアーPNPトランジスタと、それにつづくカレントミラー回路が入っています。
このバイアス回路にはそれぞれ 2×I の電流が流れるようにされていて、半分がバイポーラペアへ、半分がカレントミラー回路へ流れます。それぞれのペアは、同じテール電流 I で動作します。このフォロアー回路とカレントミラー回路には配線上、およびプロセス上の構成から発生する寄生容量成分が存在します。これらの容量成分が、このアンプの動作速度を制限する要因になります。従ってこのアンプの回路ブロックは図 15 の左側のようにあらわされます。図 15 を用いてアンプの動作を説明します。



ここで、出力アンプの入力バイアス電流が小さく、ゼロと考えることができれば、ふたつの入力段より出力される電流は同じ大きさ、逆の向きになると釣りあいます。(オフセットは無視する) 図の C は、先に説明した内部の寄生容量です。ここで右図のように帰還をかけると、バッファアンプの出力は、VA と等しくなって釣りあいます。入力は完全な差動入力となり、接続しだいで反転、非反転が可能です。これは、ふたつの入力段の入力電圧が等しくなることで、出力の電流値がバランスするからです。同じように下側の入力段のグランドに落ちている側に信号を入れるとその回路は次のように動作します。(図 16)この回路動作は、右の図にあるように、4 個のオペアンプと抵抗で構成する回路と等価ですが、それぞれの抵抗のマッチングが CMRR 性能に大きく影響を与え、またアンプ3がゲイン2倍で動作するため、帯域は 1/2 になります。この回路の V2 をグランドに接続すると、Vout=V1+V3 という加算回路になります。またこのアクティブフィードバック・アンプを使用すると、外部に抵抗等を使用せずに、ゲイン2倍の回路を組むことができ、その際の帯域の減少はありません。図 17 は、ゲインが1倍での使用を考えた構成ですが、ゲインが必要な場合は、図 18 のようにフィーバック回路を構成すれば、通常のオペアンプのように抵抗の比率でゲインを決めることができます。このようにアクティブフィードバック・アンプは、非常に汎用性の高いゲインブロックとして利用することが可能で、入力の回路構成が完全な差動であるため、大変使い勝手が良くなっています。

このアンプは、ゲインが 1 倍、-1 倍あるいは 2 倍の時は、外部に抵抗等を必要とせず、接続だけで構成することもできます。また最初に述べたように、バイポーラ gm 段に起因するひずみを小さくすることができ、高い帯域まで非常に良好な歪み特性を備えます。