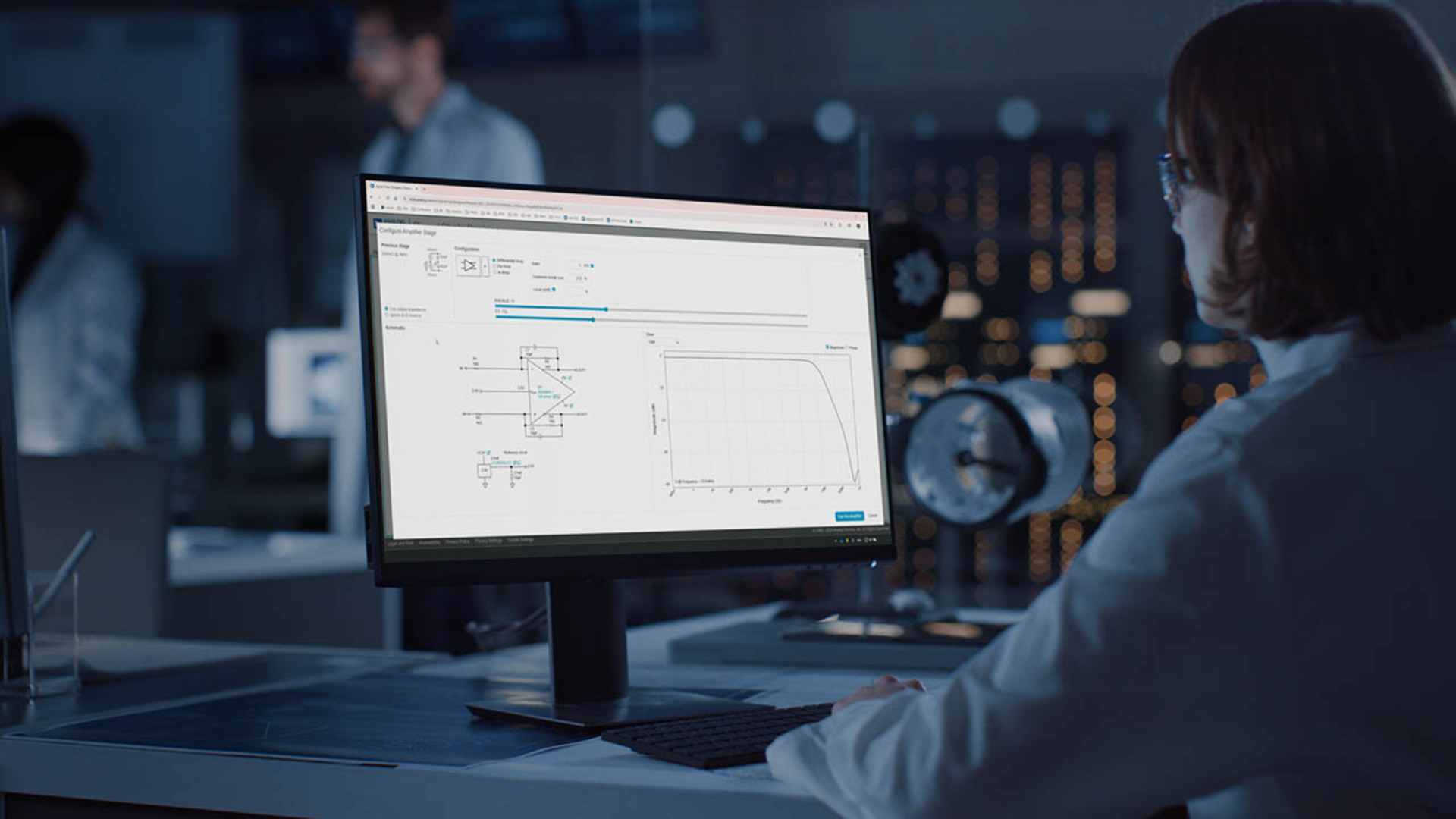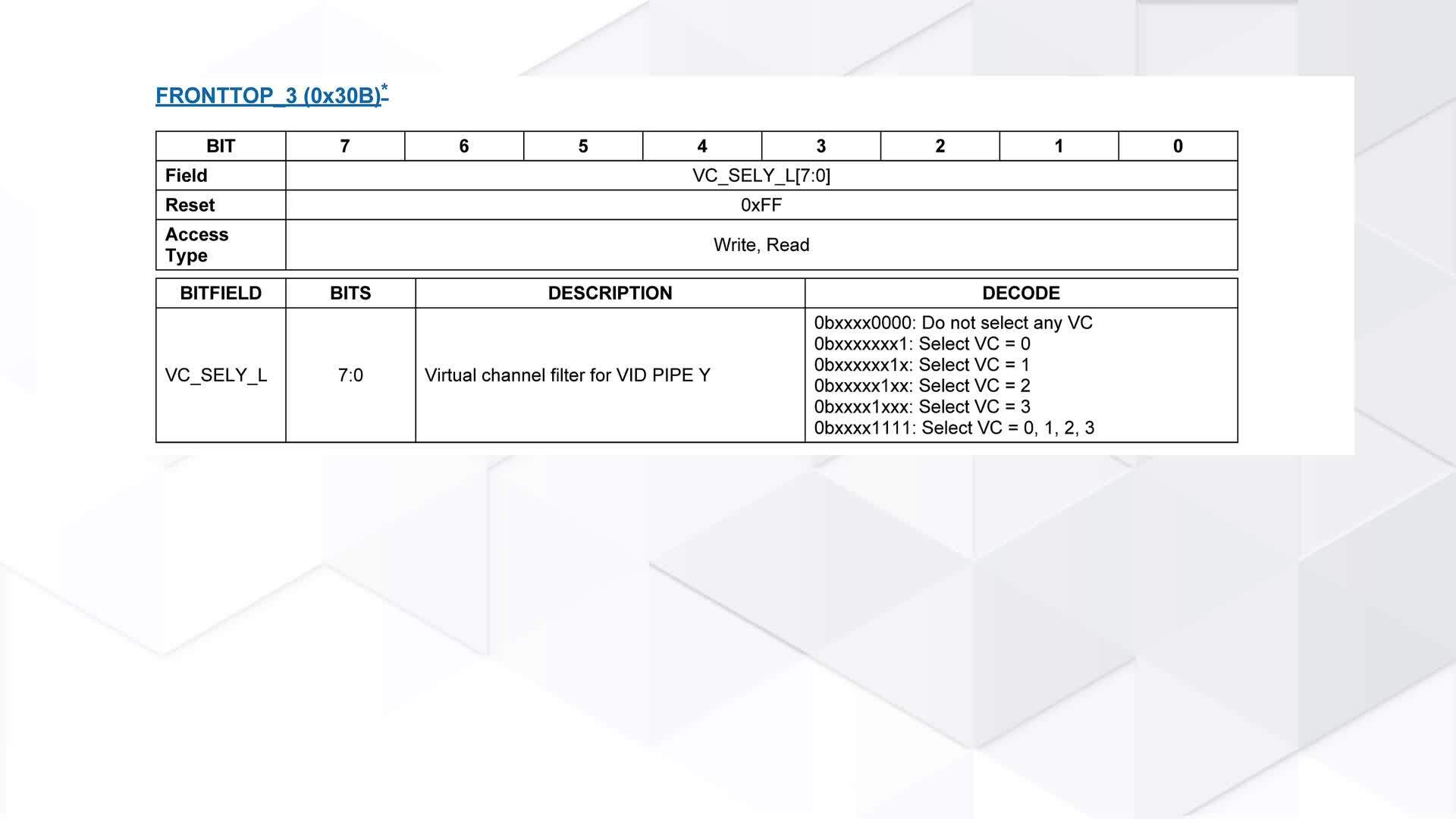要約
急激に成長するインターネットトラフィックでは、ほぼ絶え間なくデータ伝送能力が拡張されることが要求されます。データハイウェイ上でのトラフィックの混雑を避けるため、ネットワークプロバイダは、高速かつフレキシブルでコスト効率に優れた帯域幅拡張を実現する技術を必要としています。こうした技術の1つとして、高密度波長分割多重方式(DWDM)と呼ばれるデータ伝送技術があります。これは、既存のファイバインフラストラクチャを用いてネットワークのデータを増大するものです。
DWDM技術
従来の長距離ファイバ伝送システムでは、2次光学窓(1300nm帯)の単一波長(信号分散が少ない)、または3次光学窓(1500nm/1600nm帯)の単一波長(信号減衰が少ない)を使用して、一定のビットレートでデータを送信しています。より高い伝送容量を得るために、時分割多重方式(TDM)を用いてビットレートを上げることができます。あるいは、既存のファイバケーブルと並行してファイバケーブルを追加で設置することもできます(その両方を行うこともできます)。
ファイバケーブルを追加で設置するという2番目の手法には高価で時間のかかる建設工事が必要であるため、ビットレートを増やす手法の方が、既存のファイバネットワーク内で、より広い帯域幅が得られる、コスト効率に優れた方法であると思われます。ただし、高速なIC開発のための技術(たとえばコスト効率の良い完成されたプロセスなど)が欠如していたり、ファイバメディアの物理的な制限(たとえばファイバの偏光モード分散など)があったりすると、40Gbpsを超える実用的な商用伝送システムの実現は不可能です。1つのファイバリンクをたとえば2.5Gbpsから10Gbpsにアップグレードしても帯域幅の容量は4倍にしかなりませんが、高密度波長分割多重方式(DWDM)と呼ばれる伝送技術を用いると、容量を160倍にも増大させることが可能です。
DWDMは、1本の光ファイバケーブルで複数の光の波長を同時に伝えることが可能であるという物理的現象をうまく利用します。これを利用すれば、ファイバメディアを通して複数の高ビットレートの信号をそれぞれ異なる色の光に同時に乗せることが可能となります。
WDM伝送のもう1つの重要な長所は(TDMの長距離トランクと比較した場合)、「ビットレートトランスペアレンシ」であり、これは純粋な光機能によって実現するものです。この機能は光マルチプレクサやデマルチプレクサ、光ラインアンプ(OLA)、及び将来的には、超長距離リンクのための光3R再生器などのシステムで必須となる機能です。したがって、原則としてリンクにはビットレートを制限する要素は含まれず、高ビットレートを得るために光ライン部品を変更する必要はありません。
DWDMシステム部品の概要
DWDM伝送システムの基本的な要素は、光マルチプレクサ、光ラインアンプ(OLA)、及び光デマルチプレクサです(図1)。
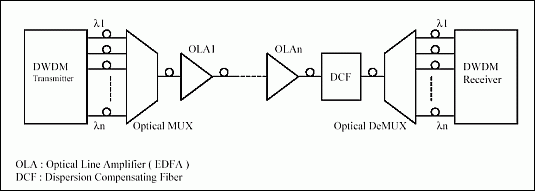
図1. 高密度波長分割多重方式(DWDM)リンクの例
光マルチプレクサは、受信したすべてのLバンド(1530nm~1565nm)とCバンド(1570nm~1620nm)の波長を、波長多重化した1つの光信号に集約します。今日のシステムでは、0.4nm以下の波長分離が実現されており、潜在的に約160種類の波長が利用可能となります。LバンドとCバンドの制限は、光ラインアンプによって定められ、これによって、LバンドとCバンドから受信した光信号だけを増幅することができます。1300nmの光学窓のための光ラインアンプは、現在も開発中です。
光ラインアンプを実現するために最も広く利用されている技術の1つは、エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)です。EDFAは、980nmまたは1480nmで動作するポンプレーザを内蔵しており、これによって電子のエネルギー準位が上昇します。波長がLバンドまたはCバンド内の光を受信すると、これらの電子は、入射光の波長を持つ光子を放射した後、より低いエネルギー帯に下がります。これによって生じる光領域の増幅は、ビットレートの影響を受けません。光マルチプレクサとデマルチプレクサの間の距離に応じて、複数のEDFAを約100kmの標準間隔でカスケード接続することができます。この方法によって、電子的な信号再生を必要とせずに、数百kmの光伝送リンクが可能となります。
EDFAの短所は、高エネルギー準位の電子が、より低いエネルギー帯へと自然に低下することによって、関係のない光ノイズを生成するということです。通常、DWDMリンクには一連のOLAが連続して含まれるため、この光ノイズは後続のEDFA内で増幅され、結果として生じるノイズの蓄積によって、OLAを含まないシステムと比較して、レシーバの信号対ノイズ比(SNR)が低下します。さらに、この光ノイズは、ロジックのローレベルよりもハイレベルに大きく影響するため、非対称になります。
光デマルチプレクサは、レシーバ側で受け取った波長多重化信号を、対応する個々の波長に変換し、トランスミッタ側で出力します。この逆多重化機能には、非常に狭い光フィルタが含まれるため、波長分離を細かくするほど、設計に多くの労力が必要となります。前述の基本的なシステム要素とは別に、DWDMシステムには、システム性能を向上し、リンクの長さを延長するために、その他の機能(光マルチプレクサ後方の光ブースタ、分散補償、または光デマルチプレクサ前方の光プリアンプシステムなど)が含まれる場合があります。
ビットレートがトランスペアレントなネットワーク(全光ネットワーク)では、トランスペアレントなDWDMポイント間接続に加えて、光アド/ドロップマルチプレクサ(OADM)や光クロスコネクト(OXC)などの要素がさらに必要となります。現在利用可能なプロトタイプでこの純粋な光機能の実現可能性を実証することができますが、今日のネットワーク機器は主に(OADMやOXCと呼ばれるものであっても)、光ではなく電子によって中核となる機能を実現しています。
さらに、超長距離のポイント間接続では、純粋な光に置き変わる完成度の高いものがないため、(ラインの距離に応じて)電子的な3R再生が必要となる場合があります。したがって、全光ネットワークは、まだ数年先の話です。ただし、全光ネットワークの一部または全部が利用可能になったとしても、ネットワークのライン端末は、引き続き光信号を電気信号に変換することが必要となります。なぜなら、光の世界以外で使用する機器は、依然として電子を利用した通信に依存しているからです。
DWDM長距離ポイント間伝送システムのためのネットワーク終端は、専用のライン終端カードまたは波長トランスポンダを用いて実現可能です。ライン終端カードは、(たとえば)中央局(CO)がDWDMリンクに対して直接送受信を行うような新しい設備に使用されます。一方、波長トランスポンダは、DWDMリンクが、古い「無色の」光ネットワークインタフェースを含んだ既存のCO機器に接続する必要がある場合に不可欠となります。以下の記述は、ライン終端カード及び波長トランスポンダに当てはまるもので、DWDMファイバネットワーク内のO/Eレシーバとトランスミッタに伴う、特定の設計課題に焦点を当てています。
DWDMトランスミッタ
DWDMシステムには、2つの機能が重要となります。1つ目は、システムのコストを低減するため、リンクを可能な限り長くして電子信号を再生する必要をなくすことです。2番目は、信頼性の高いデータ伝送をシステムが提供することです。サービス品質を向上し、ラインの距離を延長するため、順方向誤り訂正(FEC)機能を導入することができます(図2を参照)。

図2. 10GbpsのDWDMトランスミッタの例
純粋なSDH/SONETデータの場合、信号のフレーム構成内の予備バイトによって、「帯域内」順方向誤り訂正機能を実現することができます。FEC機能に必要なバイトは、オーバヘッド処理ASICによってフレームに挿入されます。プロトコルに依存しないDWDMシステムの場合、「帯域外」 FECを利用する必要があります。これによって、ビットレートが増大するだけでなく、帯域内FECに対する効率も向上します。ITU-T G.975勧告で規定されたリードソロモンFECアルゴリズムは、実現可能な帯域外FEC実装の一例です。訂正機能に必要なオーバヘッドが設けられているため、このアルゴリズムでは伝送ビットレートが7%増大します。
リードソロモンFECの代わりとしては、ITU-T G.709で規定されたディジタルラッパー機能が最も優れていると思われます。信号は、ビットレートやプロトコルに関係なく「スーパフレーム」によってラップされます。このフレームには、(FEC機能用のバイトに加えて)信号の転送(ペイロードをその宛先に送信する)に必要なアドレス指定バイトが含まれます。ディジタルラッパー機能のオーバヘッドは、一定の割合だけ伝送ビットレートを増やしますが、選択したディジタルラッパーの概念に依存することになります。選択した帯域外FEC/ディジタルラッパーの方式に関わらず、関連するアルゴリズムをサポートするためのICが追加で必要となります。あるいはトランスミッタのオーバヘッド処理ASICにその機能を内蔵する必要があります。
FECまたはディジタルラッパー処理は、伝送信号の低速パラレルデータストリーム上で実行されます。したがって、この処理機能が実行されるパラレルデータは、シリアル化して、高速な伝送信号を形成する必要があります。このタスクには、伝送クロックを生成するためのオンチップのクロックシンセサイザを備えたシリアライザが必要となります。
長距離トランクの場合、低ジッタの信号を出力することが非常に重要です。つまり、シリアライザによって生成されるジッタ、及び内蔵クロックシンセサイザに適用される外部基準クロックのジッタをできるだけ少なくすることが望ましいということになります。多くの場合、利用可能なシステム基準クロックは、これらのジッタ要件を満たさないばかりでなく、必要な周波数にも満たない場合があります。外付けのVCXOやVCSOを備えたクロック発生器を利用して、必要となる低ジッタの基準周波数を生成することが可能です。またスペースとコストを削減するために、COを内蔵した完全集積回路が現在開発中です。
シリアライザの出力段は光トランスミッタを駆動できないため、ドライバ機能が必要です。残念ながら、この機能によってジッタが追加されるため、リタイミングフリップフロップをドライバの入力段に内蔵してデータのジッタを最小限に抑えることが必要です。通常、シリアライザのシリアルクロックをこのリタイミング機能に利用しますが、シリアライザの出力とドライバリタイミングの入力間の相互接続は理想的なものでないため、クロック信号を低下させる可能性があり、これによって伝送信号のジッタ性能も低下する場合があります。したがって、リタイミング機能はオプションとすべきです。
ドライバとの統合に役立つもう1つの機能にパルス幅補正がありますが、これは光部品の非対称の立上りと立下りの遷移を補償するプリディストーションを採用しています。
最後に、シリアル信号を専用波長の光信号に変換する必要があります。最大160種の異なる波長を扱うためには、波長分離が0.4nm以下でなければなりません。これは、非常に高精度の波長安定制御を備えた光源、非常に狭いスペクトルライン幅、及び低チャープ(高速変調によるスペクトルラインのホッピング現象)を必要とします。直接変調のレーザダイオードの代わりに、電界吸収型変調器(EAM)またはマッハツェンダ変調器(MZ)をCWレーザと組み合わせることによって、上述の長距離伝送のための要件が満たされます。
モジュールに収められたこれらのトランスミッタは、温度を設定することによって特定の波長を調整するためのペルチェ素子、連続的に光を放射するレーザダイオード(CWレーザダイオード、DFB型)、及び高速電圧駆動の変調器を備えています。ペルチェ素子(熱電クーラまたはTEC)は、CWレーザダイオードを特定温度に順応する波長に設定するため、数アンペアを取り扱うことのできるドライバ回路を必要とします。調整された波長を一定に保つため、TECコントローラ回路によって温度を正確に制御する必要があります。
TECコントローラ回路は、電力FETやオペアンプなどのディスクリート部品を用いてすべての機能を実現することが必要な場合には、スペースをとる可能性があります。幸いにも、電力FETや電力制御ループを備えた省スペースのオンチップ完全集積TECドライバが利用可能であり、省スペースが重要となるモジュール統合やアプリケーション(マルチチャネルのネットワークインタフェースを備える)をサポートすることができます。さらに、波長分離が0.4nm以下のDWDMシステムや、(システムの設定によっては) 0.8nmの分離にも、波長ロック機能が必要となります。エタロンベースの制御ユニット(ファブリペローフィルタ)は、TECドライバ/コントローラ機能を利用して、トレランスウィンドウ以内に波長を維持することができます。
また別の重要なトランスミッタのパラメータとして、ユーザが決定する光送信の初期電力があります。CWレーザは、経年変化や温度変動の影響を受けずこれを持続する必要があります。CWレーザの特性曲線の勾配は、時間及び温度上昇とともに低下するため、レーザのドライバ回路は、光送信電力の平均を設定して維持する必要があります。この電力レベルは、CWレーザのモニタダイオード(光出力電力に比例)によって検出される受信光電流と、所望の光出力電力に対応する初期決定の基準値を比較する自動電力制御ループによって確保することができます。ドライバにはさらに、レーザの寿命を示すアラームフラグ、レーザの安全性のためのシャットダウン機能、CWレーザのバイアス電流のためのモニタ出力、最大レーザバイアス電流の制限設定値、及び平均光電力モニタを含める必要があります。また、光出力信号を振幅変調する場合には、低速のパイロットトーンが役立ちます。この機能によって、(たとえば) DWDMシステムでのチャネル識別が可能となります。
光変調器は通常、レーザダイオードとは異なり、50Ωのインピーダンスにマッチングされているため、EAMやMZデバイスの駆動には、直接変調のレーザドライバではなく変調器ドライバを使用する必要があります。したがって、変調器のドライバは、50Ωの負荷に対して最適化すべきで、また、電流ではなく変調電圧を出力する必要があります。EAMタイプのデバイスは、最大3Vの変調電圧を必要とし、MZタイプは最大7Vが必要です。MZ変調器では、最も狭いスペクトルライン幅を実現できますが、比較的高い変調電圧が必要となり、EAMタイプより高価になります。したがって、MZ変調器は、超長距離を必要とするアプリケーションで使用されます。
どちらのタイプも、光変調器のチャープ効果を最適化するために変調電圧のDCプリバイアスが必要です。プリバイアスを内蔵した変調器のドライバは、ドライバ出力と変調器の間に相互接続を1つだけ必要とします。この機能は、省スペースのモジュール統合を可能にし、またバイアスTネットワークの設定に通常は必要となる外付けのインダクタを排除することによって製造の手間を省くことができます。
DWDMレシーバ
従来のTDMレシーバに影響を与えるファイバの減衰や分散に加えて、上述の非対称の光ノイズによってDWDMレシーバ用の光信号に乱れが生じるため、DWDMレシーバは、より重い負担を背負うことになります。レシーバの入力感度を向上させるため、通常、その第1の素子はアバランシェフォトダイオード(APD)です。これによって、光子を電子に変換する間に、電圧制御のアバランシェ降伏によって電子を倍増させます。倍増効果を得るため、(タイプに応じて) APDに最大90Vの逆バイアスをかける必要があります。
APDへの逆バイアスは、温度に対する増倍率(利得係数「M」)を一定に保つために厳しく制御する必要があります。これには、低ノイズ、低リップル、及び高精度の電圧供給が必要となり、利用可能な基板の電源電圧(3.3Vまたは5V)からAPDの逆バイアスの高電圧を引き出す必要があります。
APD内で一定の利得を維持するため、ペルチェ素子を用いて温度制御することが可能です。また、その逆バイアスを温度の関数として変更することも可能です。2番目の方法は通常、よりコスト効率に優れた方法です。APDへの利用可能な低ノイズバイアス供給(IC)は、高精度で最大90Vの電圧を供給し、APD保護のための電流制限、アバランシェ表示フラグ、及び逆バイアス設定用のオプションのDACなどの機能を含みます。
システム管理では、受信された信号の平均電力の検出が必要です。これは、初段プリアンプ(トランスインピーダンスアンプまたはTIA)における、APDの直後に実装可能ですが、TIAの部品間に許容誤差があるため、受信電圧を測定する最も正確な方法としては、この手法は排除されます。より良い方法は、フォトディテクタのバイアス電圧源から平均光電流を直接検出することです。PINダイオードとAPDに対して小さな電流監視ICを利用すれば、平均光電流に比例した電流または電圧を出力できます。この出力によって、1µA未満の光電流についても正確に検出できるようになります。
設計者は、レシーバダイオードの回路を設計した後、OLAが出力する光ノイズに対処する必要があります。非対称性であるため、光ノイズはロジック0よりもロジック1に対してより大きなノイズフロアを示します。このため、従来のレシーバのBERを大幅に低減します。この結果、レシーバチェーンのクロック及びデータリカバリ(CDR)決定回路(入力信号に対して時間と振幅を決定することによってロジックの1と0を区別する)は、振幅決定を行う前にその決定電圧のスレッショルドレベルを調整する能力を有することが必須となります。このスレッショルド調整は、振幅決定レベルをアイパターンの中央からロジック0に向かって移動することによって、決定レベルを基準とした対称アイパターンを実現します。
このBERの最適化を正しく実装できるようにするには、CDRの前方の電子機能によって入力信号が歪まないようにする必要があります。したがって、APDと決定機能の間で、信号対ノイズ比が最小限の変動しか受けないようにすることが不可欠です。結果として、APD電流を電圧に変換するプリアンプが、ダイナミックレンジの全体にわたってリニア信号を増幅する必要があり、また後続のポストアンプが、クリッピングなしにリニア増幅をさらに追加する必要があります。電圧決定のスレッショルドの調整を容易にするため、レシーバのフルダイナミックレンジにわたってCDR入力で定電圧スイングを実現するリニア自動利得制御回路(AGC)が必要となります。
この調整は手動で行うことが可能で、経験から、またはBERを測定する自動制御ループによって、決定スレッショルドレベルを得ることができます。手動調整では、低ビットレート(2.7Gbpsまで)の場合はコスト効率が良いですが、10Gbps以上のビットレートでは、ビットレートに依存する低マージンのアイパターンの結果としてBERの自動最適化を考慮する必要があります。レシーバボード上のCDRとデシリアライザの直後にFECまたはディジタルラッパーの復号機能を実装した場合、この機能からレシーバの実際のBERを引き出すことができ、受信信号に対して訂正されたエラーの数をカウントすることができます。このエラーカウンタ情報は、次に自動スレッショルドレベルの調整を制御するフィードバックループの基準として使用することができます(図3a)。

図3a. リニアプリアンプとAGCを備えた2.5Gbps DWDMレシーバの例
スレッショルドレベルを調整する代替の方法は、プリアンプの出力端でDC電圧を制御することです。前の方法と同様、プリアンプの入力ダイナミックレンジにわたるリニア増幅に加えて、スレッショルドレベルの適応自動制御も必要となります。プリアンプの出力振幅は一定でないため、自動スレッショルドレベルの制御に代わるものはなく、FECまたはディジタルラッパーのエラーカウンタ出力からのフィードバックを受信します。
プリアンプの出力端でスレッショルドを制御する長所は、AGC機能の代わりに単純なリミティングアンプを使用できるということです。振幅決定のスレッショルドレベルがプリアンプの出力端で決定されるため、リミティングアンプのようなプリアンプ後の振幅決定回路を受け入れることができます(図3b)。

図3b. リニアプリアンプとリミティングアンプを備えた10Gbps DWDMレシーバの例
この記事は、「Communication Systems Design」の2003年6月号に掲載されたものです。